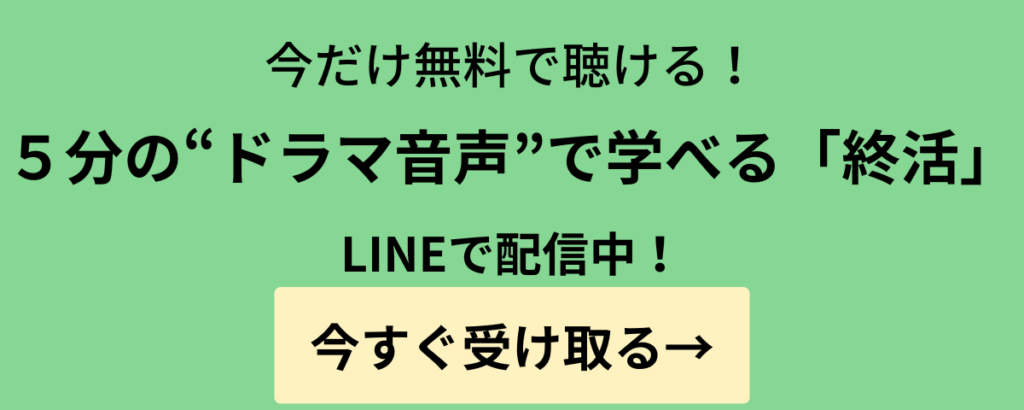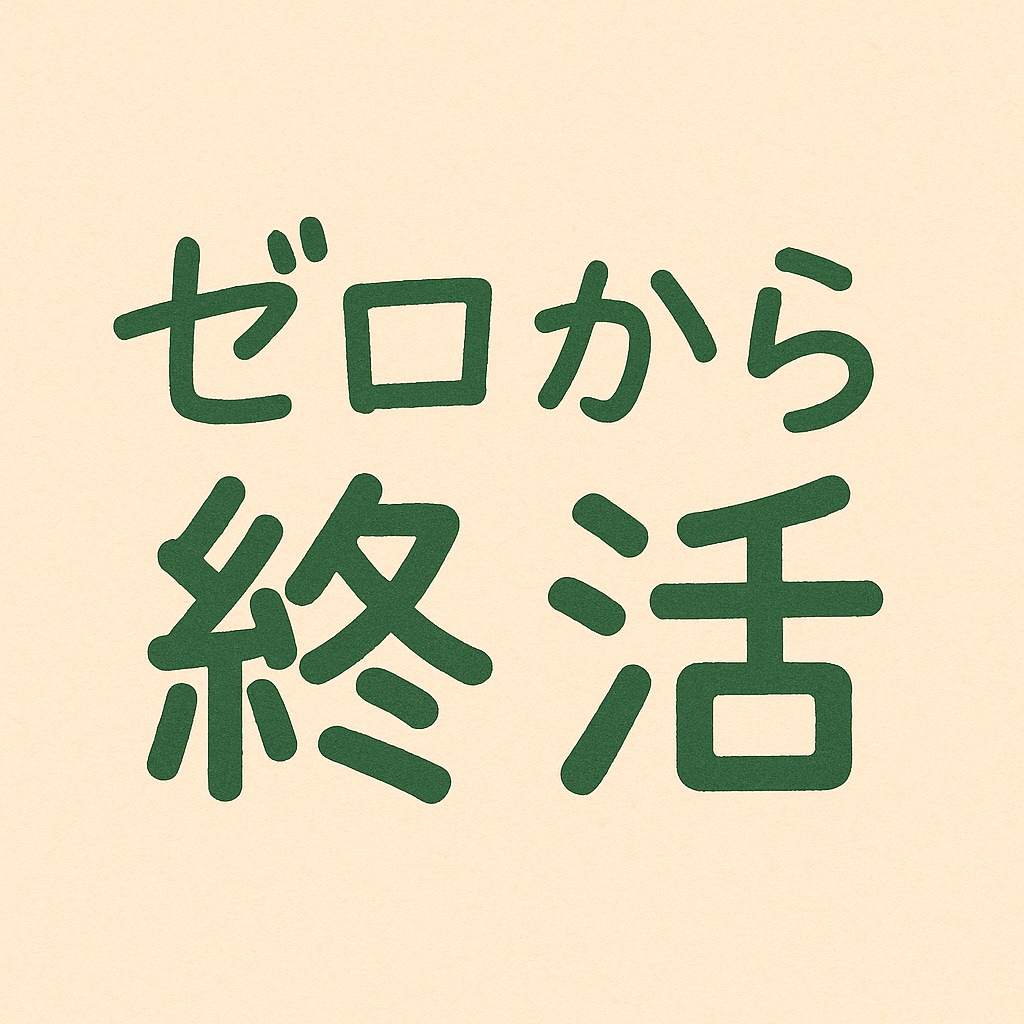遺言書は自分で書ける?法的に有効な遺言の3つの種類
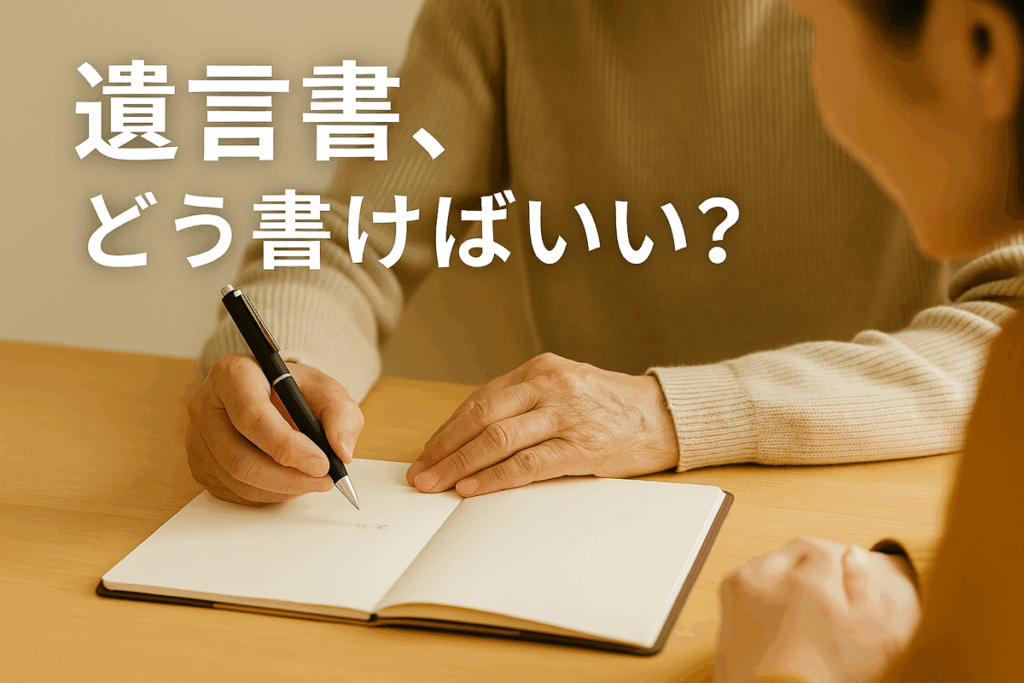
「遺言書って、自分で書いても大丈夫なの?」
──そんな疑問を持つ方は多いでしょう。
遺言書は、亡くなった後に家族がもめないための大切な書類です。
しかし、書き方を間違えると**“法的に無効”になることもある**ため、正しい知識が欠かせません。
この記事では、遺言書を作る目的と3つの法的種類、
そして自分で書く場合の注意点や費用の目安をわかりやすく解説します。
遺言書とは?残しておく目的とメリット
遺言書とは、自分の死後に財産をどう分けるか、誰に何を残すかを明確に記しておく書類です。
正式に残しておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、本人の想いを確実に伝えられます。
なぜ今、遺言書を作る人が増えているのか
近年、相続トラブルの件数は年々増えています。
背景には、次のような理由があります:
- 財産の価値が多様化(不動産・保険・預金・株など)
- 相続人が複数の地域に分かれている
- 「兄弟間の不公平感」を避けたいという意識の高まり
つまり、“自分の想いを形にして残す”時代になっているのです。
法的に有効な遺言書の3つの種類
日本の法律で有効とされている遺言書の形式は3つあります。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。
① 自筆証書遺言(自分で書くタイプ)
最も手軽に作成できる遺言書です。
紙とペンがあればすぐに書け、費用もかかりません。
ただし、全文を自分で書く必要があるため、
誤字脱字・形式ミスで無効になるケースも多いです。
- メリット:費用がかからず簡単に始められる
- デメリット:形式不備・紛失・改ざんリスクあり
② 公正証書遺言(公証役場で作成)
公証人と証人2名の立ち会いで作成する、最も確実な方法です。
法律的に有効性が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
- メリット:無効になりにくい/法的トラブル防止
- デメリット:費用がかかる(約2〜5万円+財産規模で変動)
③ 秘密証書遺言(内容を秘密にできる)
内容を誰にも見せずに作成し、公証役場で“存在のみ”を証明してもらう方法です。
遺言の内容を秘密にしたい方に向いています。
- メリット:内容を誰にも知られずに作成できる
- デメリット:形式ミスで無効になるリスクが高い
自分で書く場合の注意点
全文自筆・日付・署名押印が必要
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。
パソコンや代筆は無効になります。
また、日付を「令和6年春」など曖昧にすると法的に不備になるため、
必ず「令和6年4月15日」のように正確に記載しましょう。
法務局での保管制度を活用する
2020年から始まった「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、
法務局で安全に保管できます。
- 保管手数料:1通につき3,900円
- 検認(裁判所手続き)が不要になるメリットあり
「書いたけどどこにあるかわからない」という事態を防げます。
遺言書を作成する流れと費用
公証人・証人・手数料の目安
| 項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 公証人手数料 | 財産額によって変動 | 約2〜5万円前後 |
| 証人報酬 | 2名分が必要 | 各5,000〜10,000円程度 |
| 登録印紙代・謄本代 | 書類発行時 | 約1,000〜2,000円 |
※財産が多い場合はさらに加算されます。
専門家に相談するタイミング
次のような場合は、司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
- 財産の種類が多い(不動産・株式など)
- 相続人が複数・関係が複雑
- 特定の人に多く残したい
専門家のチェックを受けるだけで、無効リスクを大幅に減らせます。
まとめ|遺言書は“家族を守る最後の手紙”
遺言書は、“お金や財産を分けるための書類”ではありません。
家族が迷わずに、穏やかに前へ進むためのメッセージです。
「まだ早い」と思っても、今のうちに準備をしておくことで、
将来の不安が安心に変わります。
📚 参考・出典
・ 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」・ 日本公証人連合会「公正証書遺言の作り方」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。