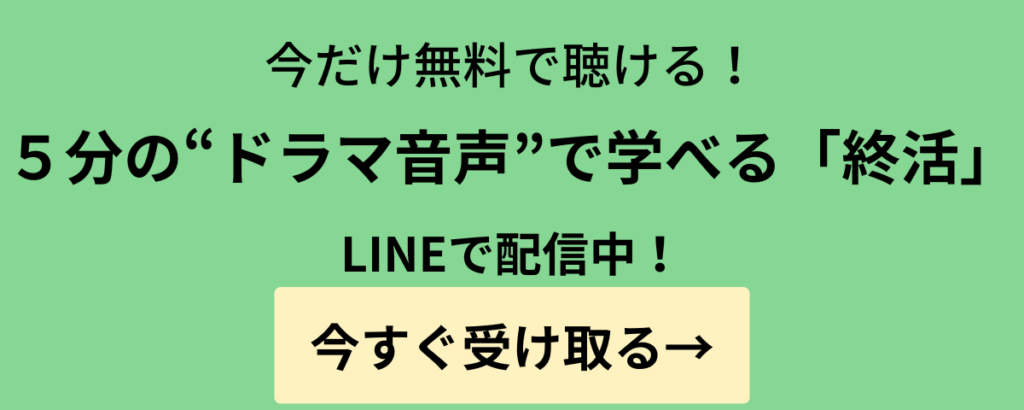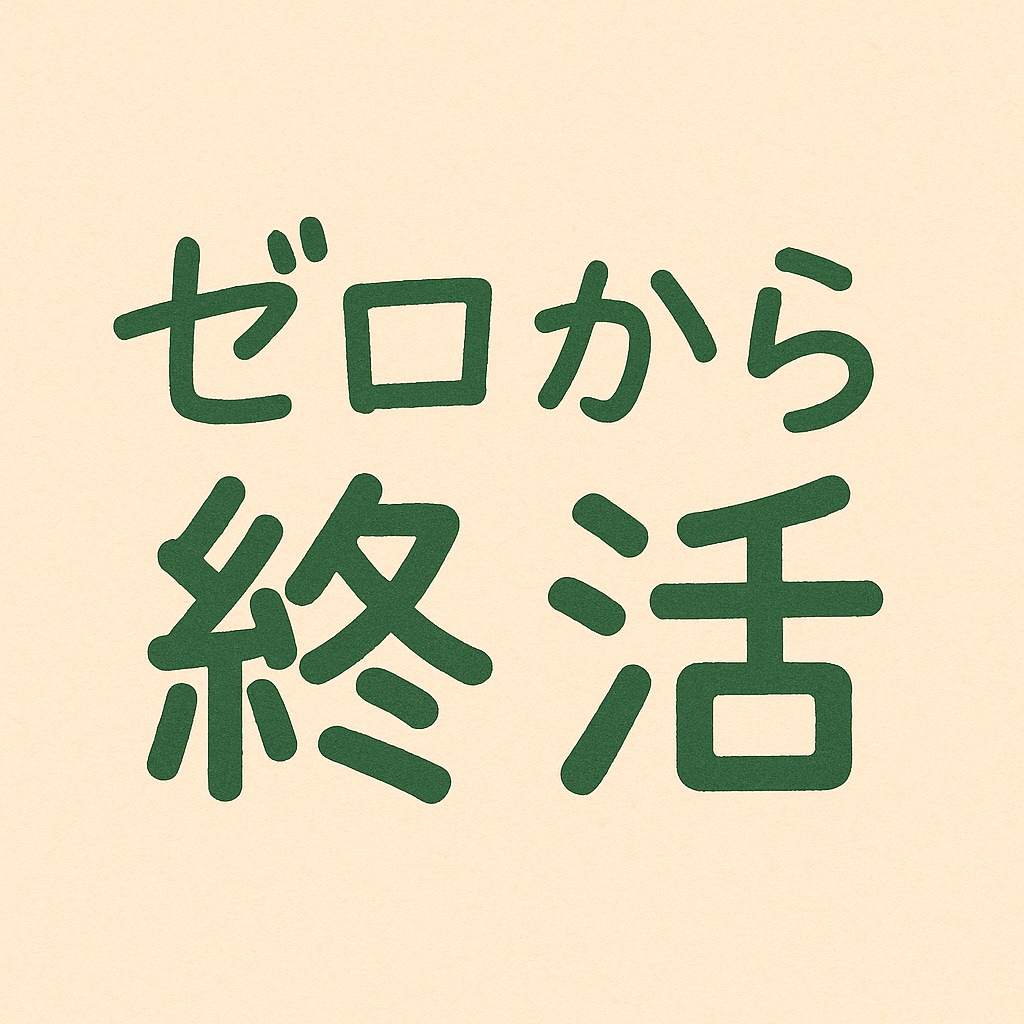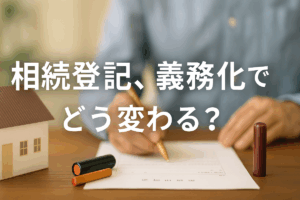相続登記の義務化とは?期限・罰則・費用をわかりやすく解説
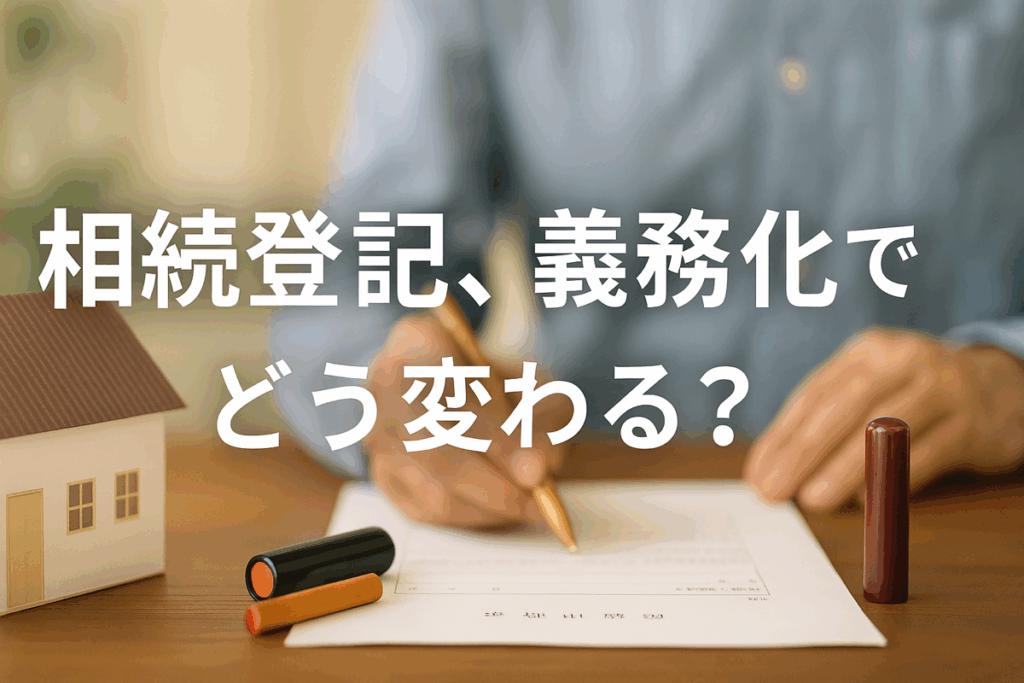
「親の不動産、名義がそのままだけど大丈夫かな?」
──そう感じたことはありませんか?
実は、2024年4月から相続登記が義務化されました。
これまで「登記は任意」だった時代から、「登記をしなければならない」時代へと変わっています。
この記事では、相続登記の義務化で何が変わったのか、
いつまでに手続きが必要なのか、
そして費用や罰則についても、初心者にもわかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?法律の背景を解説
2024年4月から義務化された理由
2024年4月1日から、「相続登記の申請義務」が正式に施行されました。
これは、土地や建物の名義を放置したままにする人が増え、
所有者不明の不動産が全国で増加したことが背景にあります。
放置されたままの不動産は、売買・開発・公共事業の妨げになり、
社会的な問題となっていました。
そのため国は、名義をきちんと整理して管理できるように制度を整えたのです。
「相続人不明土地問題」を防ぐため
相続登記を怠ると、誰がその土地の所有者か分からなくなります。
相続人が10人、20人と増えるうちに連絡も取れず、
「相続人不明土地問題」 と呼ばれる社会課題に発展しました。
義務化によって、こうした問題を防ぎ、
家族や地域社会の資産を守ることが目的とされています。
相続登記の義務化で変わること
登記申請の期限は“相続開始を知ってから3年以内”
相続登記は、相続が発生した日ではなく、
「自分が相続で不動産を取得したと知った日」から3年以内 に申請する必要があります。
たとえば、親が亡くなり、
その不動産を自分が相続することを知った日から3年以内が期限です。
3年を過ぎると、法律上「義務違反」とみなされます。
正当な理由なく怠ると過料(罰金)の可能性
期限内に登記を行わなかった場合、
10万円以下の過料(罰金) が科される可能性があります。
ただし、次のような「正当な理由」があれば免除されることもあります:
- 相続人同士の話し合いがまとまらない
- 災害や病気などで手続きができなかった
- 登記に必要な書類が揃わなかった
「義務化=すぐ罰則」ではありませんが、
できるだけ早めに準備しておくことが安心です。
相続登記の流れと必要書類
① 相続人の調査
まずは、誰が相続人になるのかを確認します。
戸籍謄本を取得し、家系図のように相続関係を整理しておくとスムーズです。
② 遺産分割協議書の作成
相続人全員で「不動産を誰が相続するか」を話し合い、
その内容を遺産分割協議書にまとめます。
全員の署名と押印が必要になります。
③ 登記申請
法務局に必要書類を提出して登記申請を行います。
申請書・戸籍・印鑑証明書・固定資産評価証明書などを準備します。
👉 手続きは自分で行うことも可能ですが、
不安がある場合は司法書士に依頼するのが安心です。
費用の目安と手続き方法
自分で行う場合/司法書士に依頼する場合の比較
| 手続き方法 | 費用目安 | メリット |
|---|---|---|
| 自分で行う | 数千円〜(登録免許税のみ) | 費用を抑えられる/知識が身につく |
| 司法書士に依頼 | 3〜7万円前後(物件数により変動) | 書類不備やミスを防げる/スムーズに完了 |
登録免許税の計算例
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の**0.4%**が基本です。
例)評価額2,000万円の土地 →
2,000万円 × 0.4% = 8,000円
建物と土地を両方登記する場合、それぞれに税がかかります。
まとめ|義務化時代は“放置しない”が最善の相続対策
相続登記の義務化は、家族にとって「責任」と「安心」を両立させる制度です。
期限を守って登記を行うことで、将来の相続トラブルを防ぐことができます。
もし「まだ名義を確認していない」という場合は、
まずは登記簿をチェックしてみましょう。
“放置しない”という小さな行動が、家族の安心につながります。
📚 参考・出典
・
法務省「相続登記の申請義務化Q&A」
・
e-Gov法令検索「民法(第907条ほか)」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。