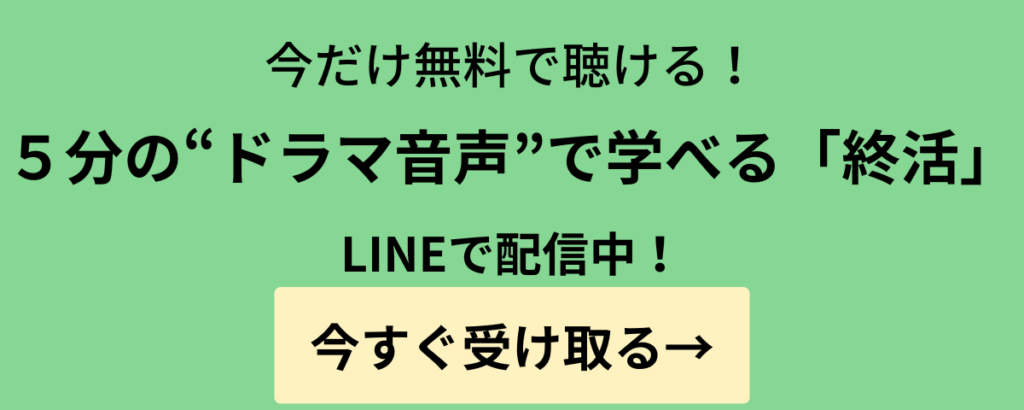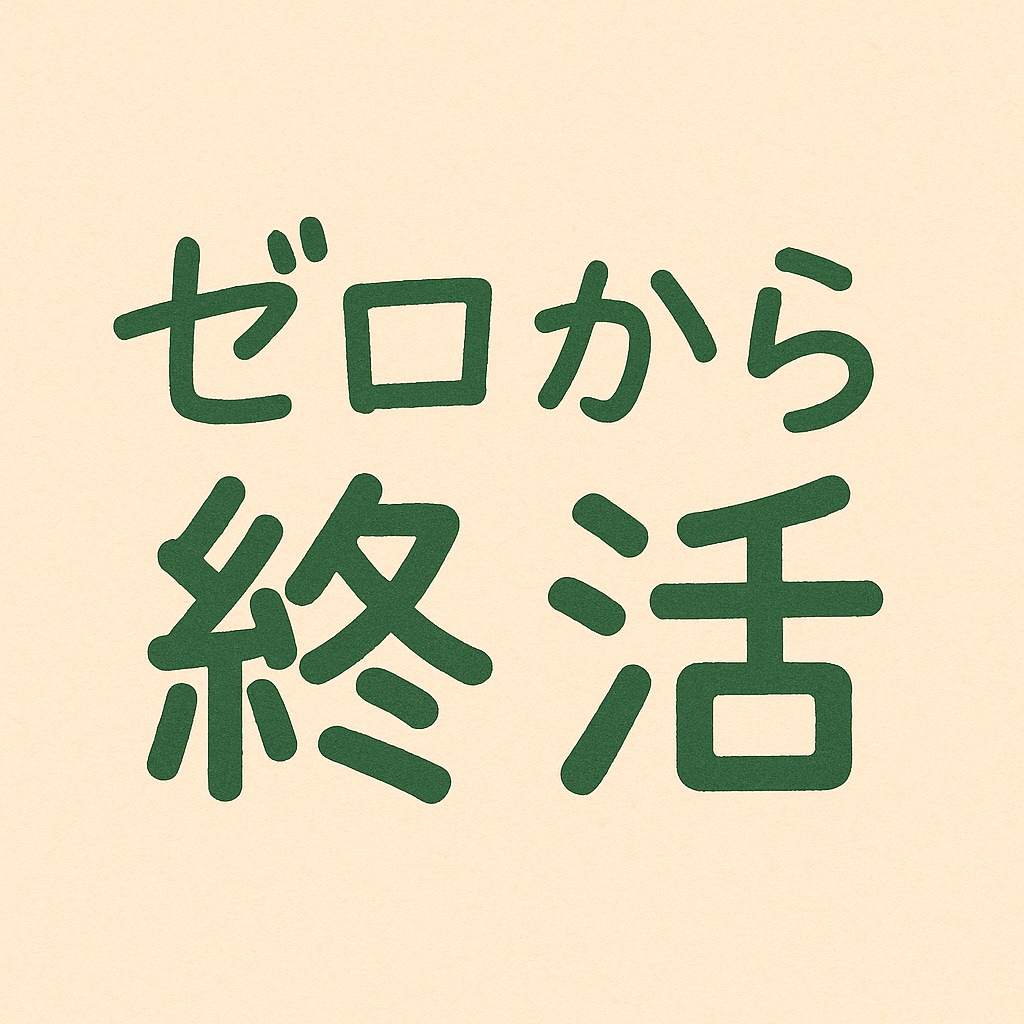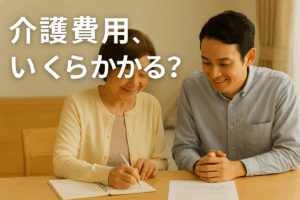葬儀費用の平均はいくら?見積もりで失敗しない3つのポイント
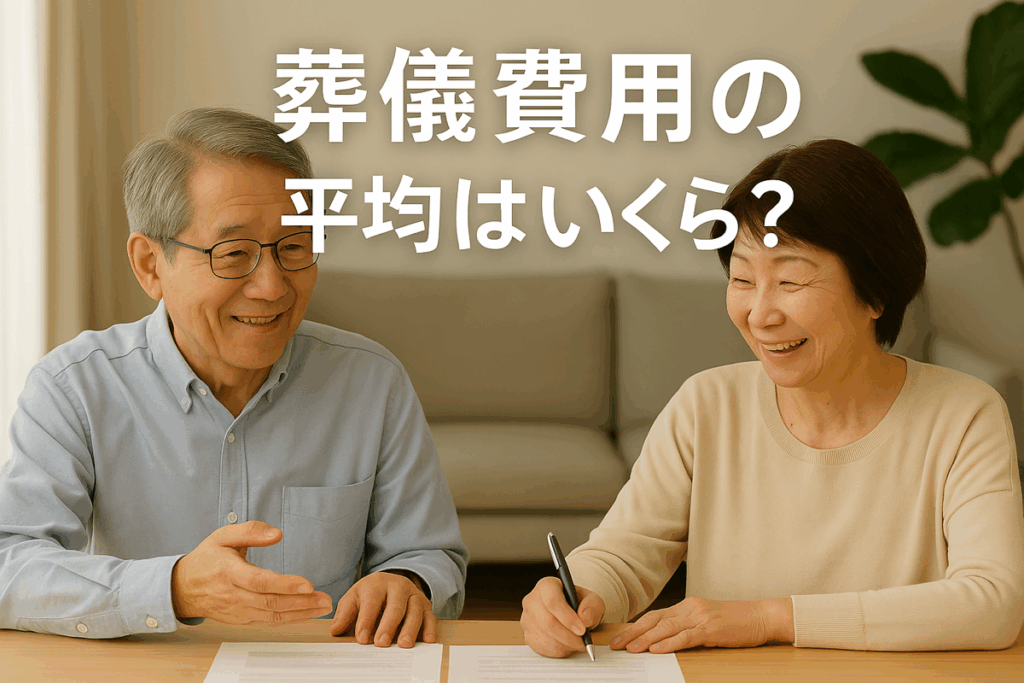
「もしものとき、葬儀っていくらかかるの?」
──そう聞かれて、すぐに答えられる人は少ないかもしれません。
実際、葬儀費用は「形式」や「人数」「地域」によって大きく異なり、
平均額を知らないまま見積もりを取ると、思わぬ出費につながることもあります。
この記事では、葬儀費用の全国平均や内訳をわかりやすく紹介しながら、
多くの人が見積もりで失敗しやすい3つの落とし穴、
そして費用を抑えながら安心できる葬儀を行うためのポイントを解説します。
葬儀費用の全国平均はいくら?
一般葬・家族葬・直葬の平均費用
日本消費者協会の調査によると、葬儀の全国平均費用は以下の通りです。
| 形式 | 平均費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般葬 | 約120〜150万円 | 通夜・告別式を行い、参列者が多い形式 |
| 家族葬 | 約80〜100万円 | 家族・親族中心。近年最も選ばれている形式 |
| 直葬(火葬式) | 約20〜40万円 | 通夜や式を行わず、火葬のみを行う簡易形式 |
地域差もあり、都市部では高め、地方ではやや低めの傾向です。
費用の内訳(葬儀社・祭壇・会場・返礼品など)
葬儀費用の主な内訳は次の通りです。
- 葬儀社基本料(搬送・手配など)
- 祭壇・棺・骨壺などの備品費用
- 会場使用料・火葬料
- 返礼品・飲食接待費
- お布施(宗教者への謝礼)
これらをすべて含めると、実際の支払い総額は平均より高くなる傾向があります。
見積もりで失敗しやすい3つの落とし穴
① 基本プランに含まれない追加料金
見積書の「基本プラン」には、意外と必要な項目が含まれていないことがあります。
たとえば、火葬料や安置日数の延長、返礼品の数など。
「基本プラン◯万円」と書かれていても、実際には20〜30万円上がるケースも少なくありません。
② 参列人数を見誤る
「家族葬の予定だったのに、思ったより参列者が増えた」というケースも多く、
返礼品や料理の追加で費用が膨らむことがあります。
最初の見積もり段階で、“最大人数”を想定しておくのが安心です。
③ 葬儀後の支払い・相続費用の見落とし
葬儀費用を支払った後、すぐに相続手続きや遺品整理の費用が発生する場合があります。
「葬儀で使いすぎた…」とならないよう、葬儀後の支出も見越して予算を組んでおきましょう。
葬儀費用を抑えるためのポイント
複数社の見積もりを比較する
同じ条件でも、葬儀社によって金額差は大きく異なります。
最低でも2〜3社に見積もりを取り、総額と内訳を比較しておくことが大切です。
最近は「オンライン見積もり」や「電話相談」で簡単に比較できるサービスも増えています。
事前相談で希望を明確にする
「どんな葬儀を望むのか」を事前に話し合っておくことで、
不要な費用を抑え、親の希望に沿った形にできます。
たとえば、
- 花を多く飾りたい
- 宗教者の有無
- 食事や会場の規模
をあらかじめ整理しておくだけでも、葬儀後の後悔を減らせます。
葬儀社を選ぶときのチェックリスト
「総額提示」「キャンセル対応」の有無を確認
見積もり段階で「総額提示(追加費用なし)」と明記されているかをチェックしましょう。
また、急な事情でキャンセルになった場合の対応条件も確認しておくと安心です。
口コミ・実績を参考にする
近年では、口コミサイトや比較サイトで葬儀社の評判を調べることができます。
「担当者の対応が丁寧」「追加請求がなかった」などの声がある葬儀社を選ぶと、
トラブルのリスクを減らせます。
まとめ|“費用の見える化”が家族の安心につながる
葬儀費用は「分かりづらい」「人に聞きづらい」ものですが、
平均や内訳を知るだけで、心の準備と費用の見通しが立ちます。
見積もりは“比較する”ことで初めて意味を持ちます。
早めに情報を集め、希望に合った形を選ぶことで、
親の想いに寄り添った温かい葬儀が実現できます。
📚 参考・出典
・
公益財団法人 日本消費者協会「第12回 葬儀についてのアンケート調査(2023)」
・
経済産業省「特定サービス産業動態統計調査(冠婚葬祭業)」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。