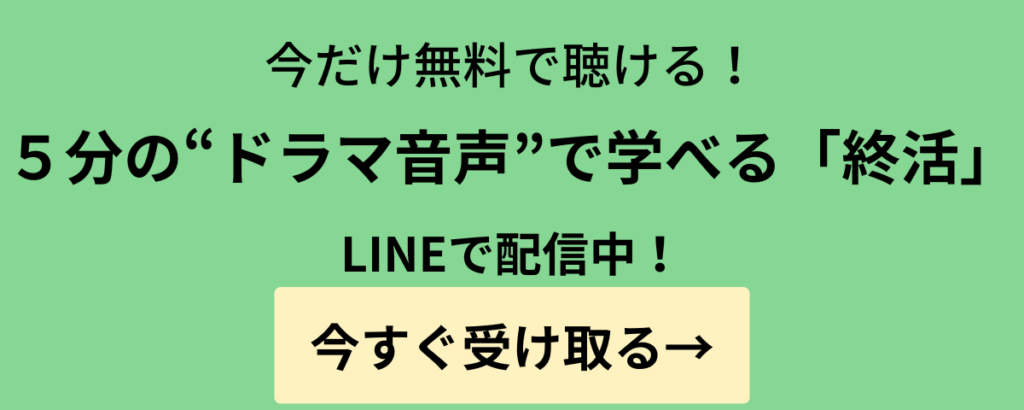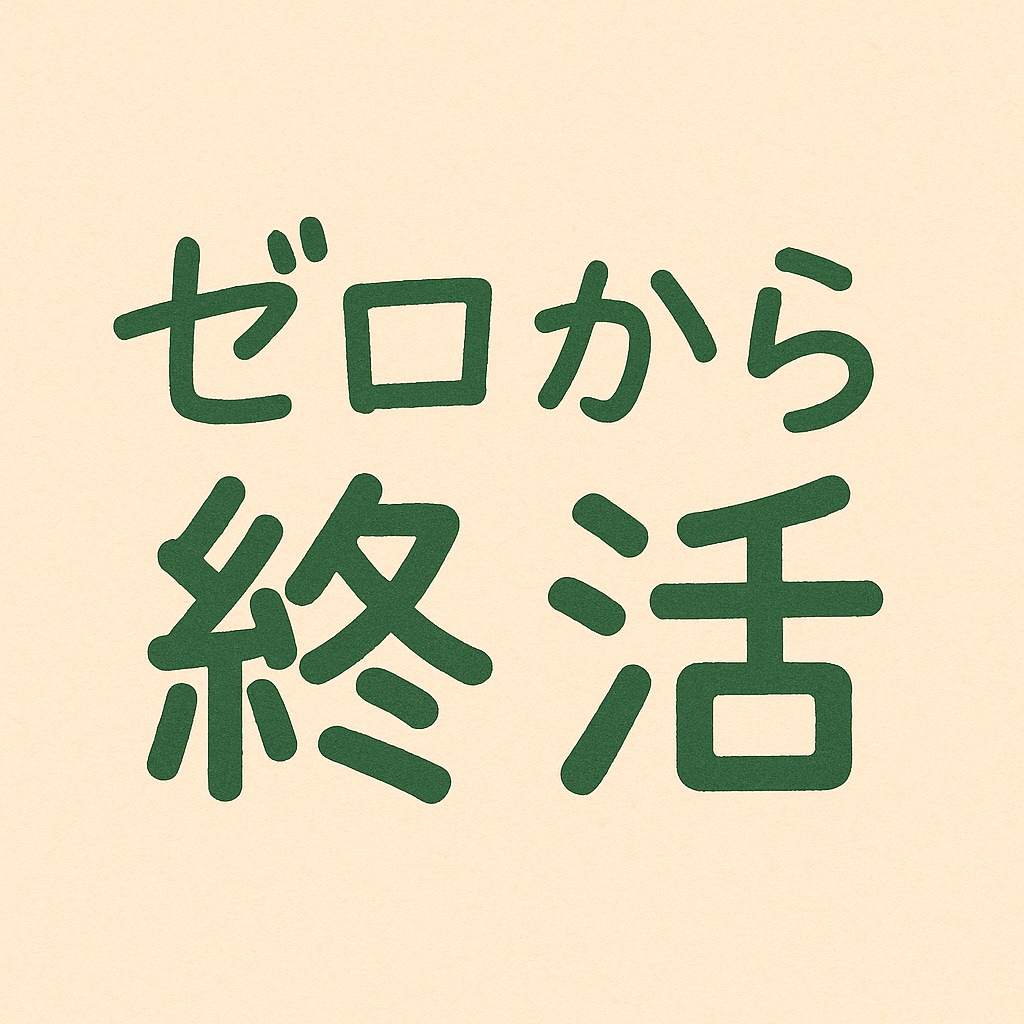不動産の名義放置は危険?相続トラブルを防ぐ3つの対策
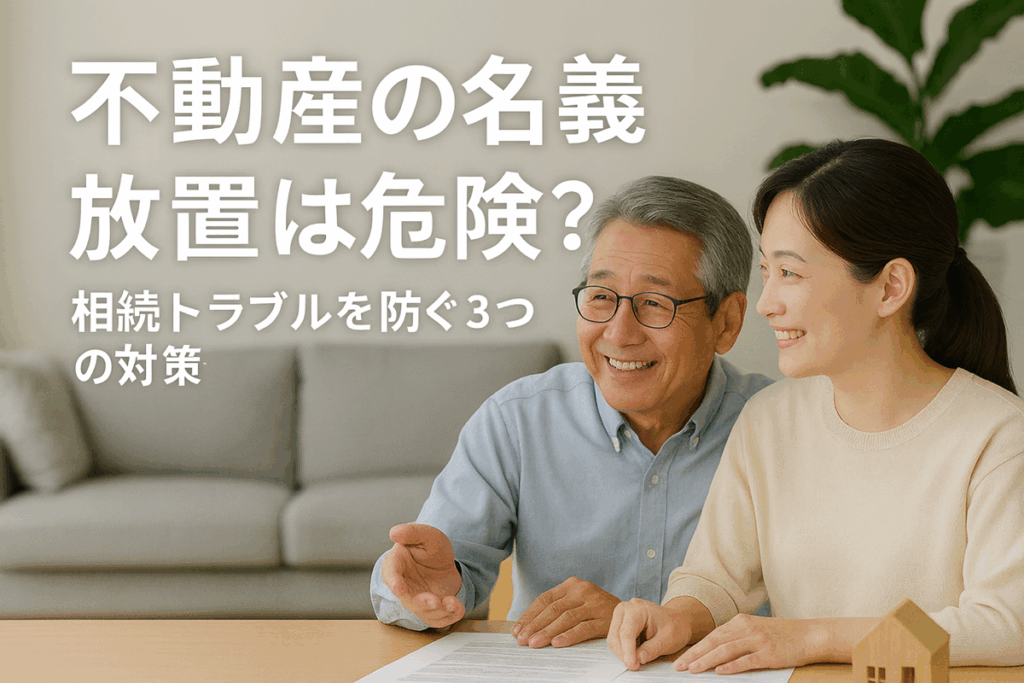
「おじいちゃん名義のままだから、特に問題ないと思ってた」
──そんな声をよく耳にします。
けれど、不動産の名義を放置することは、将来の相続トラブルの“火種”になりかねません。
売りたい時に売れない、登記ができない、相続人が増えて話がまとまらない…。
実は、放置されたままの不動産が原因で家族が困るケースは全国で急増しています。
この記事では、親や祖父母の名義のままになっている不動産をお持ちの方へ、
名義放置が招くリスク、実際に起こったトラブル、
そして今すぐできる3つの対策をわかりやすく解説します。
不動産の名義を放置するとどうなる?
誰のものかわからない」状態になる
名義が亡くなった人のままの場合、
その土地や建物の所有者が法律上“確定していない状態”になります。
つまり「誰のものとも言えない」グレーな状態。
売却も贈与も、相続登記も止まったままです。
売却・登記・相続すべてが止まるリスク
名義が古いままだと、売買契約やローンの利用ができません。
さらに、名義人が亡くなっているために手続きに相続人全員の同意が必要になります。
一人でも連絡が取れないと、登記や売却はストップ。
結果、資産価値が下がってしまうこともあります。
相続人が増えると話がまとまらなくなる
名義を放置したまま次の相続が発生すると、
相続人がどんどん増えていきます。
10人、20人と増えるうちに、連絡すら取れなくなるケースも。
たった一筆の登記を怠っただけで、
家族全員が手続きに巻き込まれる事態になるのです。
実際にあった名義放置トラブル事例
祖父名義のまま放置して相続人が10人以上に
ある家庭では、祖父名義のまま20年以上放置された土地がありました。
祖父が亡くなり、その後祖母・父・叔父が相次いで亡くなった結果、
相続人は孫世代まで含めて10人以上に。
手続きのたびに印鑑や戸籍の確認が必要になり、
登記が完了するまでに3年かかったそうです。
家を売るのに数年かかったケース
別の事例では、実家を売却しようとした時点で、
名義が“父の父(つまり祖父)”のままであることが発覚。
相続登記を行うために、遠方に住む親戚まで署名・捺印を依頼しなければならず、
売却完了まで2年以上を要しました。
その間に老朽化が進み、売却価格は大きく下がってしまいました。
相続トラブルを防ぐ3つの対策
① 相続登記を早めに済ませる
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
「相続開始を知ってから3年以内」に登記しなければ、
**罰則(10万円以下の過料)**が科される可能性もあります。
登記手続きは司法書士に依頼すれば数万円で済む場合も多く、
「後回しにしない」ことが最大のトラブル防止策です。
② 財産・不動産の一覧を作る
どの名義の不動産があるのか、どこに土地があるのかを
家族で共有できる一覧にしておくことも大切です。
地図・登記簿謄本・固定資産税の明細などをまとめておくだけで、
将来の相続手続きがスムーズになります。
③ 家族で定期的に話し合う
「そろそろ登記を整理しておこうか」
この一言が、後々の大きな安心につながります。
不動産は“親のもの”ではなく“家族の未来資産”。
早めに話し合うことで、家族全員が安心できる形を選べます。
放置してしまった場合の解決方法
司法書士に相談するタイミング
名義が古いまま数十年経っている場合は、
まず司法書士に相談しましょう。
登記簿を確認すれば、誰が相続人なのか・どう進めるべきかを明確にできます。
相続関係が複雑になっていても、
「相続放棄」「遺産分割協議書」などのサポートを受ければ、
整理可能なケースも多いです。
限定承認という選択肢もある
もし不動産に借金や税金の負担がある場合、
限定承認という方法を取ることもできます。
これは、プラスの財産の範囲でマイナスの負債を返す制度で、
「相続するけど借金は超えない」という安心な選択肢です。
まとめ|名義放置は“家族の負担”につながる
不動産の名義を放置してしまうと、
想像以上に家族の手間と時間がかかります。
早めに登記を済ませることで、
相続トラブルを防ぎ、家族の安心を守ることができます。
もし「うちも名義が昔のままかも…」と思ったら、
今が最初の一歩を踏み出すタイミングです。
📚 参考・出典
・
法務省「相続登記の申請義務化について」
・
法務省「相続登記の申請義務化Q&A」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。