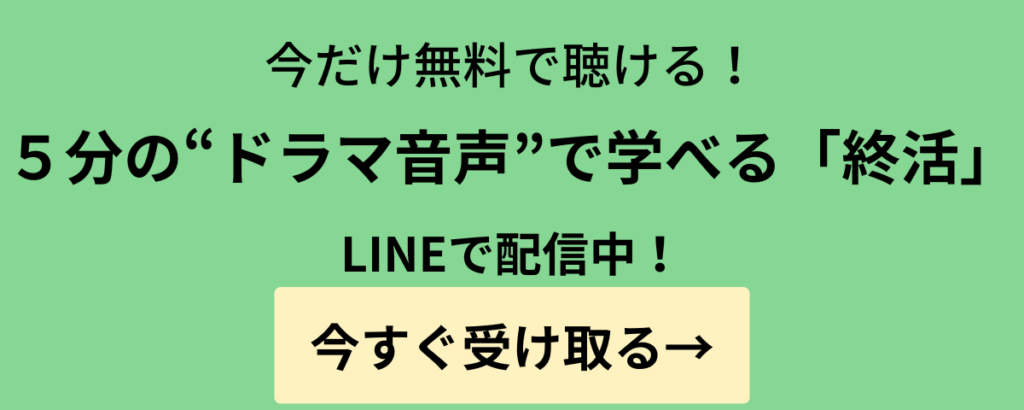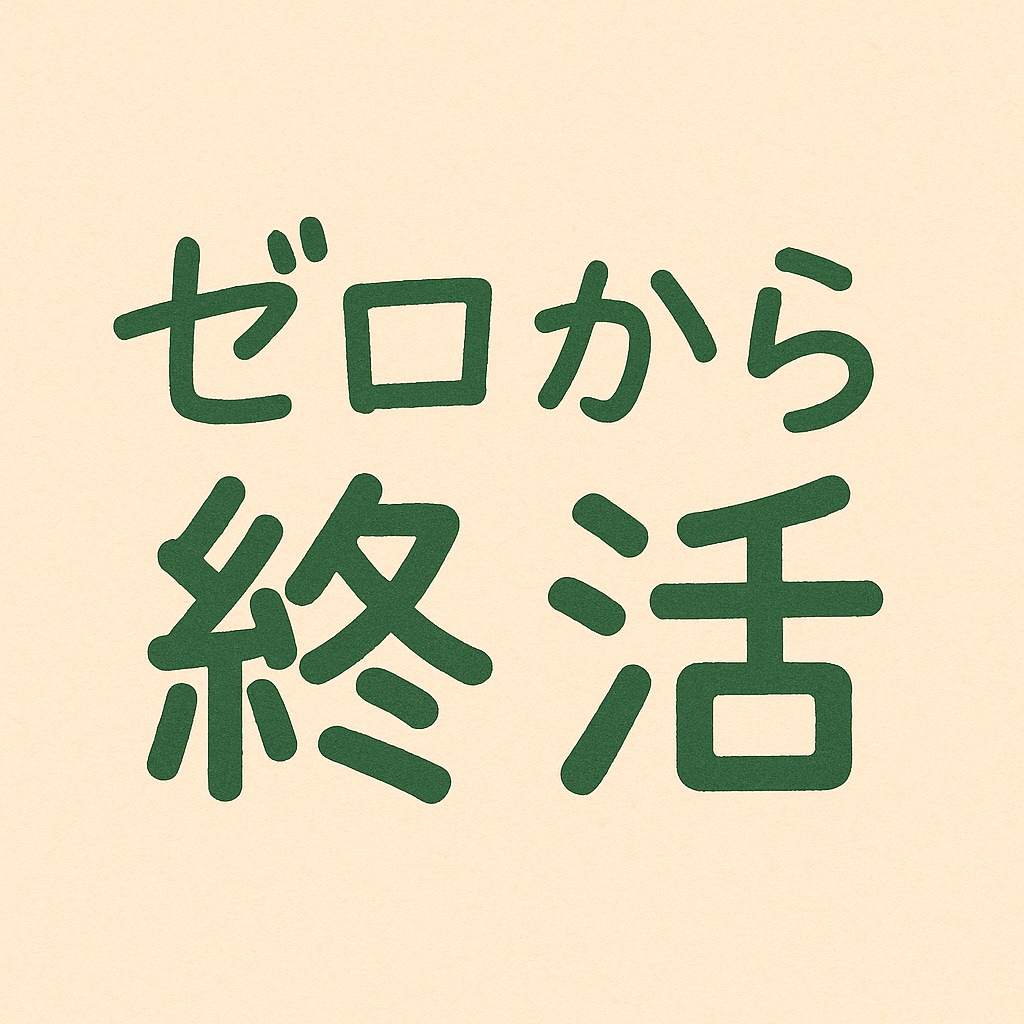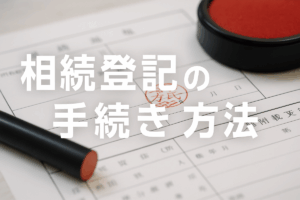相続放棄と限定承認の違い|家族を守る選択肢をわかりやすく解説
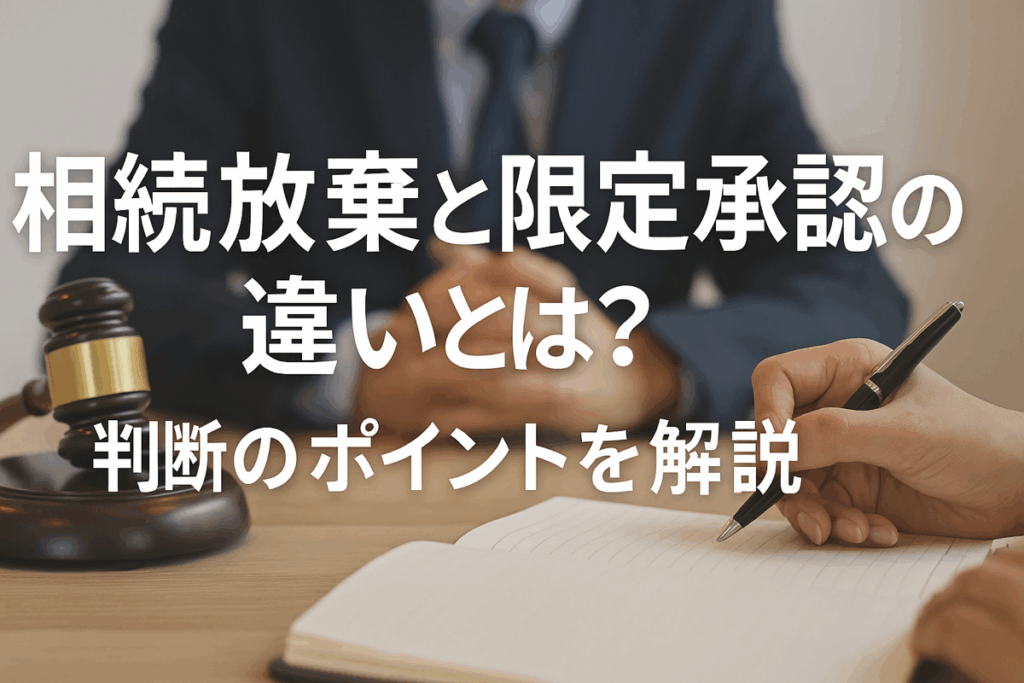
「親の借金があるかもしれない」「相続を受けるか迷っている」
そんなときに知っておきたいのが、**「相続放棄」と「限定承認」**という2つの選択肢です。
どちらも“相続人を守るための制度”ですが、内容や手続きが異なります。
この記事では、相続放棄と限定承認の違い、選ぶときの判断ポイント、
そして家庭裁判所での手続き方法をわかりやすく解説します。
相続放棄と限定承認の違いとは?
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も一切引き継がないという手続きです。
家庭裁判所に申述を行うことで、最初から相続人ではなかったことになります。
たとえば、父親が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすればその借金を背負うことはありません。
ただし、一度放棄すると取り消しはできず、プラスの財産も受け取れない点に注意が必要です。
限定承認とは
限定承認とは、**「プラスの財産の範囲でのみ借金を返す」**という制度です。
つまり、相続した財産を超える負債がある場合でも、自分の財産から補う必要はありません。
「父の家は残したいが、借金があるか不明」という場合には、
この限定承認が有効な選択肢になります。
ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要で、
相続放棄より手続きが複雑になります。
どちらを選ぶべき?判断のポイント
財産と負債のバランスを確認
最初に行うべきは、被相続人の財産と借金の全体像を把握することです。
預金・不動産・保険などの資産に対して、負債がどの程度あるかを整理します。
財産より負債が多い場合 → 相続放棄を検討
財産の方が多い・残したい家がある → 限定承認を検討
家族全員の同意が必要な場合も
限定承認は、すべての相続人が一緒に手続きする必要があります。
1人でも反対が出ると成立しないため、家族間の話し合いが欠かせません。
逆に、相続放棄は個人単位で手続き可能です。
手続きの流れと期限
家庭裁判所への申述手順
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所で「申述書」を提出することで手続きを行います。
申述書には被相続人の情報、相続人の署名、相続開始を知った日などを記載します。
必要書類は、戸籍謄本・住民票・債務証明書などです。
3ヶ月以内の判断が重要
相続放棄・限定承認は、**「相続開始を知った日から3ヶ月以内」**に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎると、**単純承認(すべてを相続したとみなされる)**扱いになるため注意しましょう。
専門家に相談すべきタイミング
司法書士・弁護士それぞれの役割
- 司法書士:書類作成や登記のサポート
- 弁護士:相続人間の調整や紛争対応
相続放棄や限定承認は、法律上の手続きが関わるため、
少しでも不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。
相談費用と依頼の流れ
司法書士・弁護士への相談費用は、1〜3万円程度が一般的です。
初回相談で「どの制度が適しているか」を判断してもらい、
その後の書類作成・申立てをサポートしてもらう流れがスムーズです。
まとめ|家族を守るための“正しい選択”
相続放棄も限定承認も、「家族に負担を残さない」ための制度です。
大切なのは、期限内に正しい判断を下すこと。
不安な場合は、専門家に相談しながら早めに行動しましょう。
相続は“遺された人の問題”ではなく、家族全員で考える準備です。
📚 参考・出典
・
裁判所「相続の放棄の申述」
・
裁判所「相続の限定承認の申述」
・
弁護士法人直法律事務所「相続放棄と限定承認の違いとは?」
・
日本司法書士会連合会「相続する人|相続登記相談センター特設サイト」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。