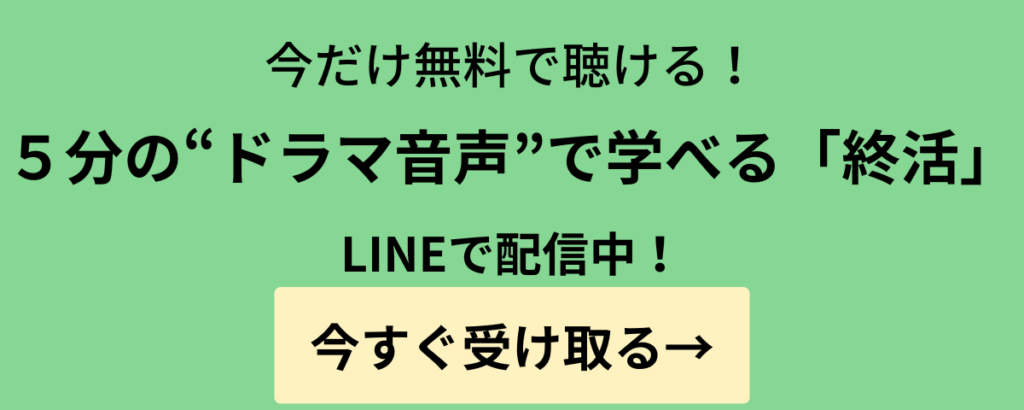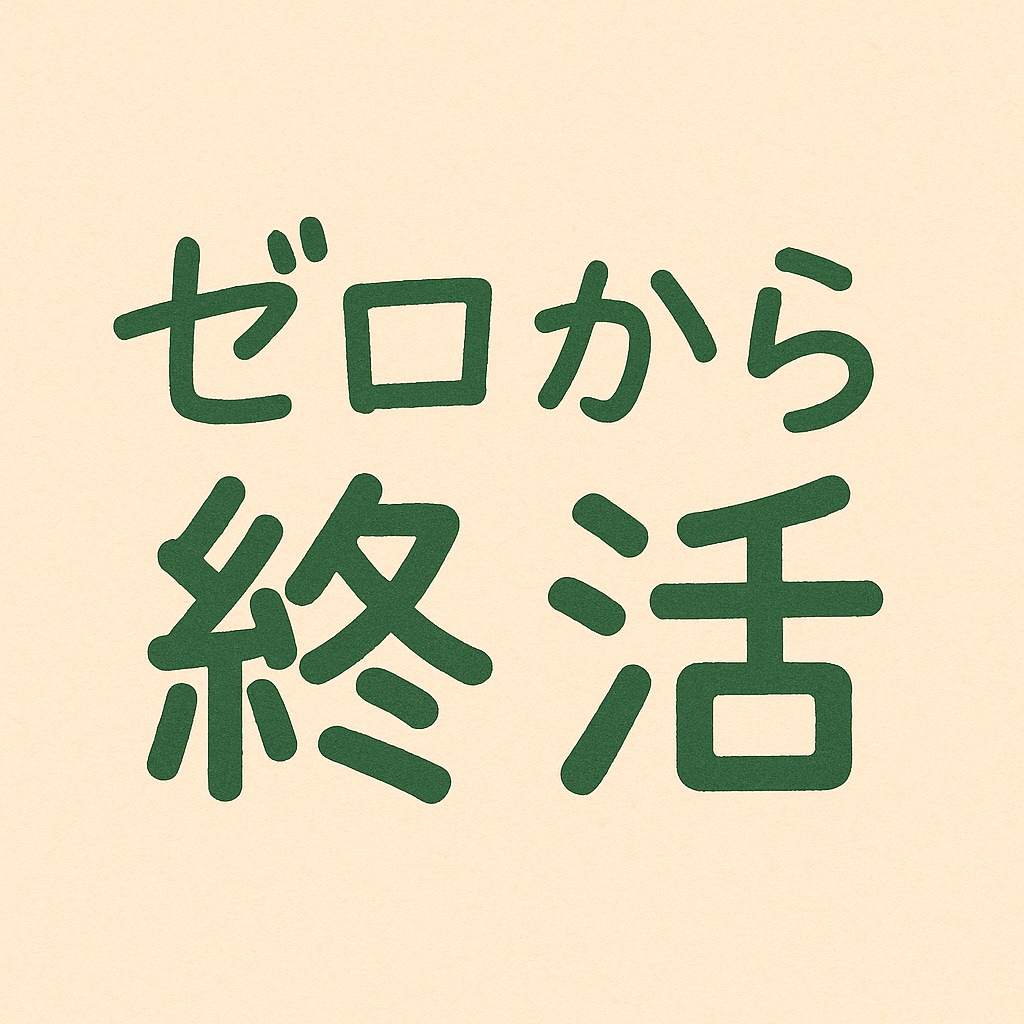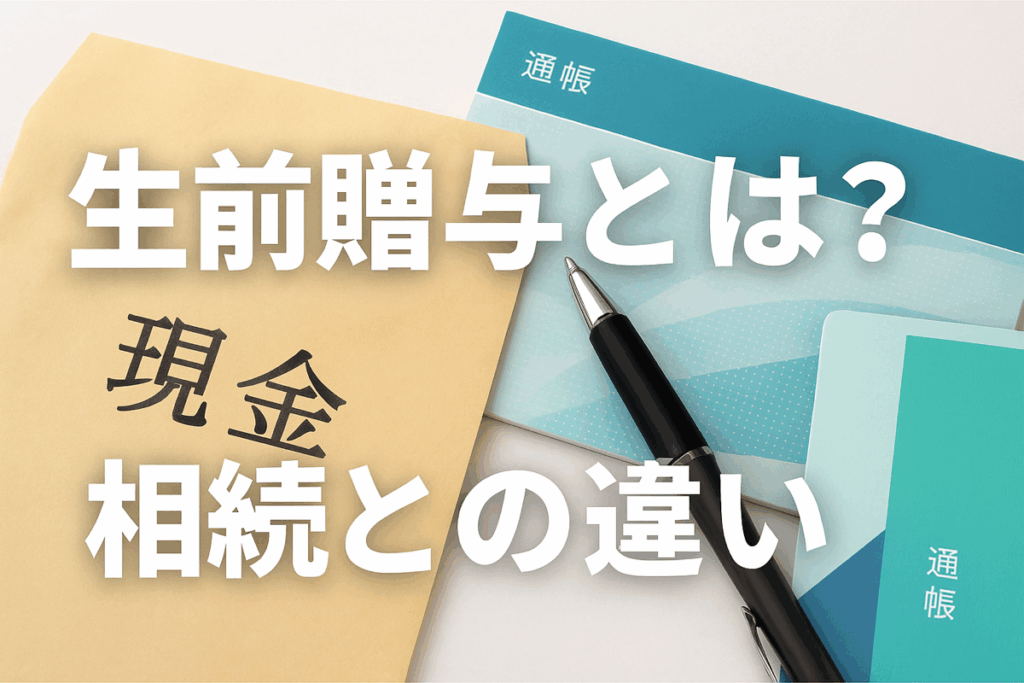相続税はいくらからかかる?基礎控除と節税対策を解説
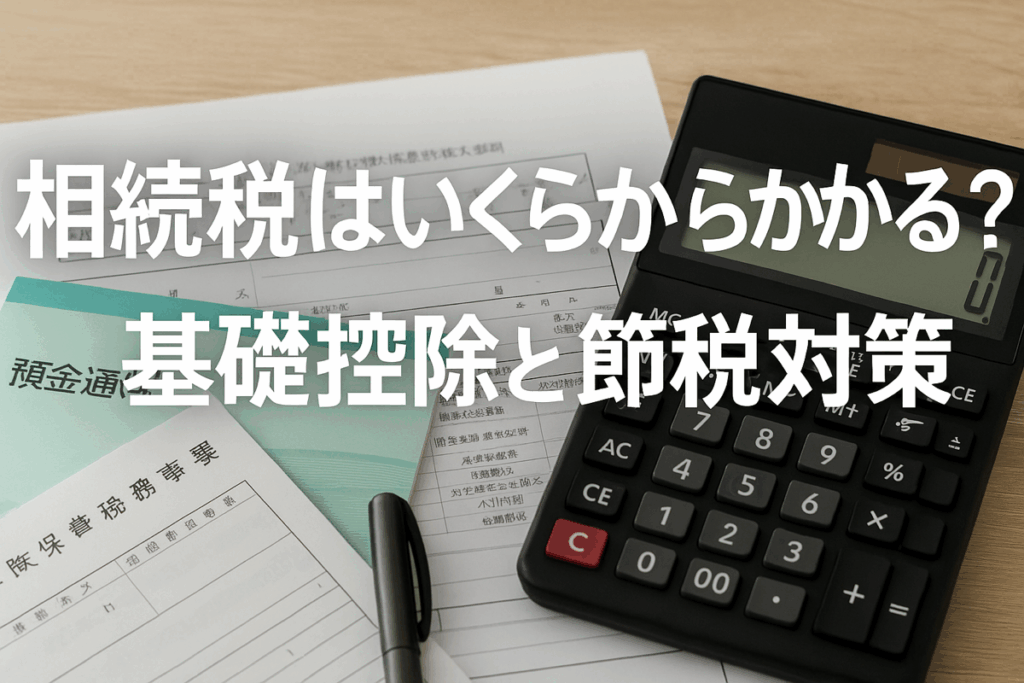
「うちは一般家庭だから、相続税なんて関係ないでしょ?」
──そう思っていませんか?
実は、ここ数年で相続税の課税対象は一般家庭にも広がりつつあります。
都心や住宅地に土地を持っているだけでも、
相続税がかかるケースは少なくありません。
この記事では、
「相続税はいくらからかかるのか?」という基本から、
控除の計算方法・節税のコツまで、初心者にもわかりやすく解説します。
相続税はいくらからかかる?
課税対象となる財産とは
相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に課される税金です。
対象となるのは、現金や預金だけではありません。
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 車・貴金属
- 生命保険金(非課税枠を超える分)
つまり、「相続=お金持ちの話」ではなく、
自宅や土地を持っている一般家庭でも関係する税金なのです。
課税価格の算出方法
相続税の課税価格は、次のように計算します。
(相続財産の総額 − 債務・葬式費用)− 各種控除 = 課税価格
この課税価格が「基礎控除額」を超えると、相続税が発生します。
基礎控除の仕組み
計算式の覚え方
相続税には、「基礎控除」という非課税枠があります。
この控除額は、次の計算式で求められます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合(3人):
👉 基礎控除額は 3,000万円+600万円×3=4,800万円
つまり、相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
配偶者控除など主要な控除
さらに、以下のような特別な控除制度もあります。
- 配偶者控除:最大1億6,000万円まで非課税
- 小規模宅地等の特例:自宅や事業用地の評価を最大80%減額
- 生命保険金の非課税枠:「500万円 × 法定相続人の数」まで
これらを組み合わせることで、相続税を大幅に減らすことができます。
相続税の計算例
一般家庭モデルケース
例:相続財産が6,000万円、相続人が3人の場合
👉 基礎控除:4,800万円
👉 課税価格:6,000万円 − 4,800万円 = 1,200万円
課税対象となる1,200万円に対して、
法定相続分ごとの税率(10〜55%)で税額を計算します。
このケースでは、税額は数十万円程度に収まることが多いです。
複数相続人がいる場合
相続人が多いほど、基礎控除額が増えるため、
家族の人数も節税要素のひとつになります。
また、遺産分割をきちんと行うことで、
各人が利用できる控除枠を最大限に活かせます。
節税の基本対策
生前贈与の活用
生前贈与を使えば、少しずつ財産を渡すことで相続財産を減らせます。
年間110万円までの贈与は非課税のため、
長期的に続けることで大きな節税効果が期待できます。
教育・住宅資金の特例なども活用すれば、
より大きな金額を非課税で贈与することも可能です。
生命保険・不動産評価の見直し
生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)を上手に利用すると、
現金よりも有利に資産を残せます。
また、不動産の評価方法を見直すことで、
相続財産全体の評価額を下げることができる場合もあります。
まとめ|“知ること”が最大の節税対策
相続税対策は、特別な人だけの話ではありません。
「いくらから課税されるか」「どんな控除が使えるか」を知るだけで、
支払う税金を大きく減らすことができます。
そして何よりも、家族が揉めないための備えになります。
今のうちに一度、家族で財産の全体像を確認してみましょう。
📚 参考・出典
・
国税庁「財産を相続したとき」
・
国税庁「配偶者の税額軽減」
・
国税庁「小規模宅地等の特例」
・
国税庁「相続税のあらまし」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。