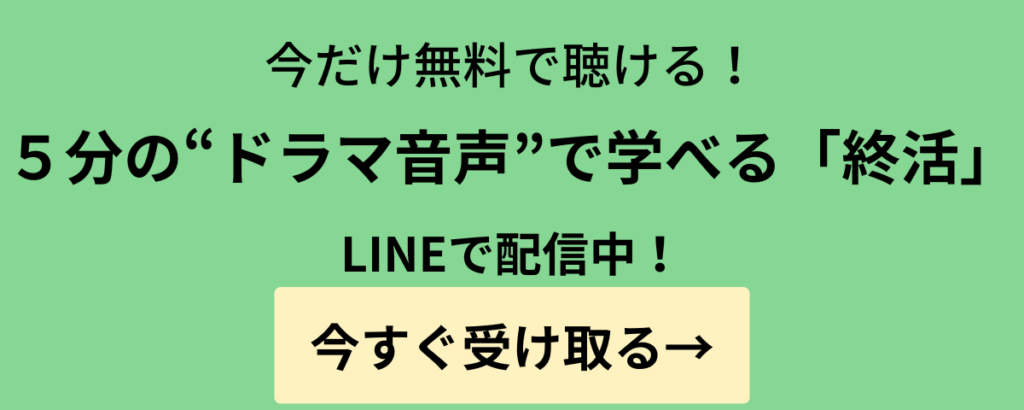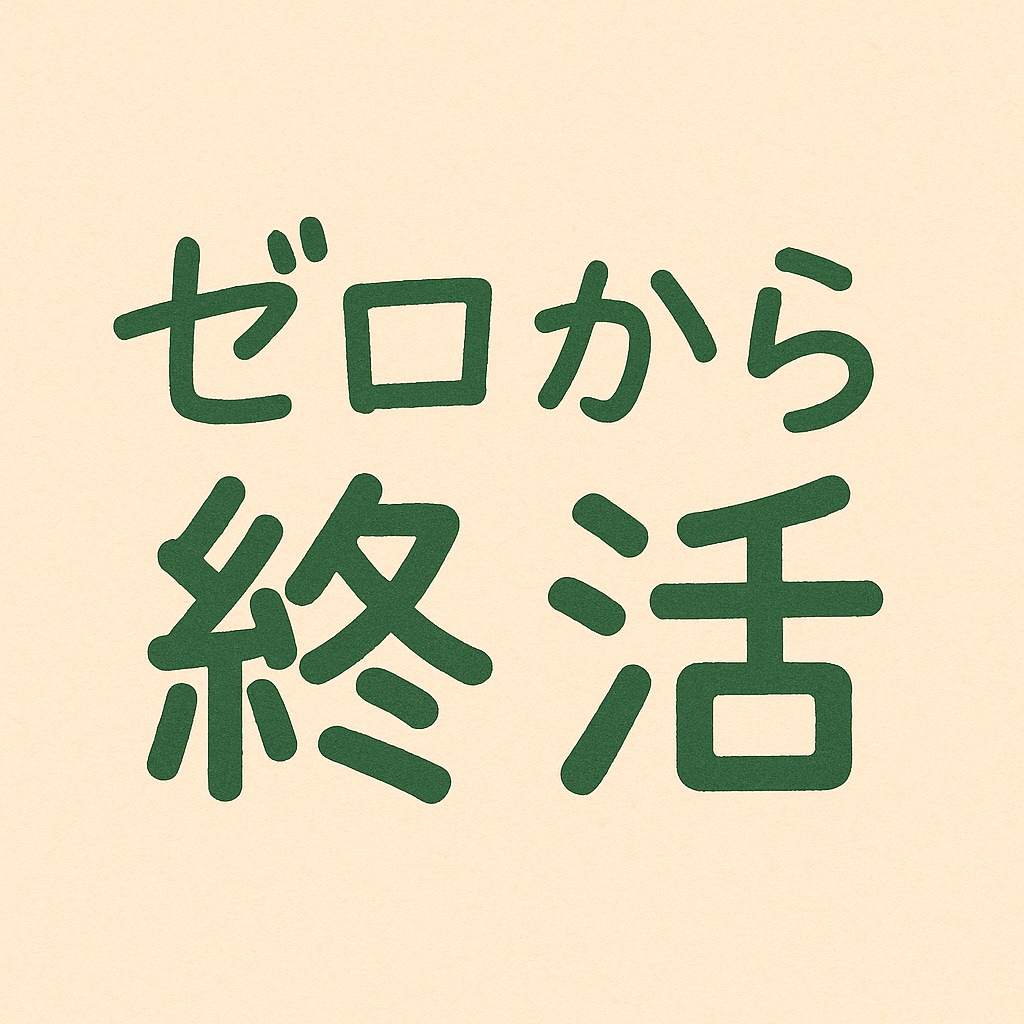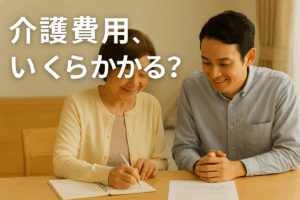延命治療とは?家族が後悔しないために話し合うべきこと
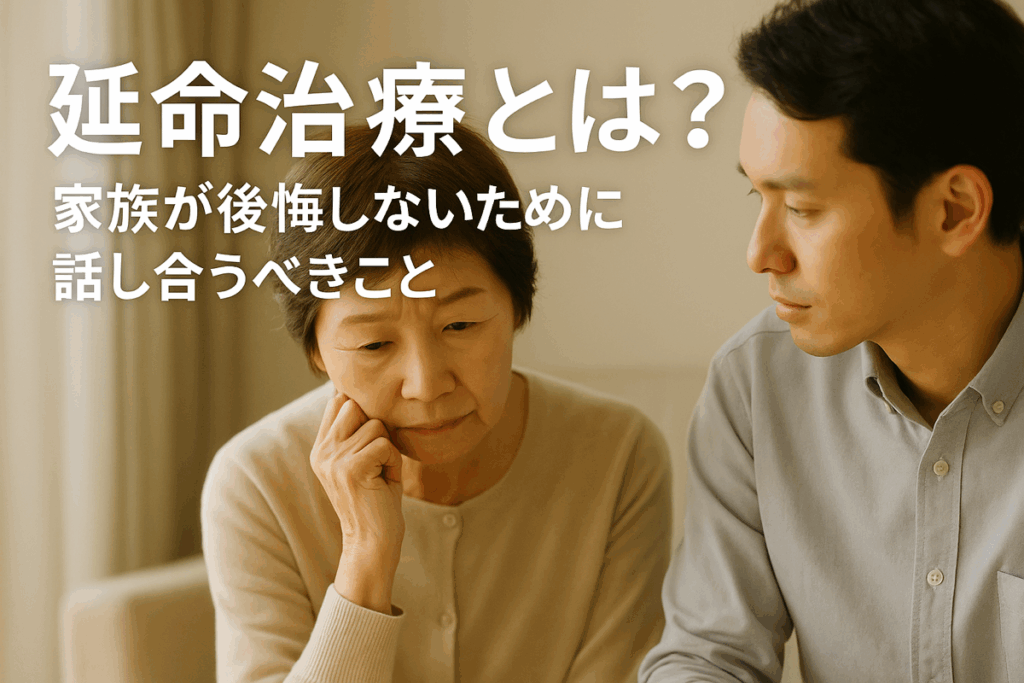
「お父さんの延命治療、どうしますか?」
──突然、医師からそう聞かれたとき、すぐに答えられる人は多くありません。
延命治療は「命を延ばすための医療行為」ですが、
その意味や範囲、そして“どこまで望むのか”は家族によって違います。
この記事では、延命治療の基本的な内容から、
家族で話し合うときに知っておきたいポイント、
そして後悔しないためにできる準備までをやさしく解説します。
延命治療とは?わかりやすく解説
延命治療の主な種類(人工呼吸器・経管栄養・点滴など)
延命治療とは、病気や老衰などで自然に命が尽きる状態になったとき、
生命を維持するための医療行為を指します。
代表的なものは次の通りです:
- 人工呼吸器:呼吸ができなくなったときに機械で酸素を送る
- 経管栄養:食事ができなくなったときにチューブで栄養を送る
- 点滴:水分や薬を体に入れて生命活動を支える
これらは命をつなぐ一方で、身体への負担や苦痛を伴う場合もあります。
延命治療の目的と限界
延命治療の目的は、命を救うこと、または一時的に生命を維持することです。
しかし、すべてのケースで「回復」を意味するわけではありません。
たとえば、
- 意識が戻らないまま長期間治療が続く
- 痛みや苦痛を感じる状態が続く
など、本人の尊厳をどう守るかが大きな課題になります。
延命治療をめぐる家族の葛藤
「やる・やらない」どちらにも後悔がある理由
家族が「延命治療をする/しない」を決めるとき、
どちらの選択にも後悔の気持ちは残るものです。
「もっとできたのでは…」
「苦しませてしまったのでは…」
そうした感情が長く心に残るケースもあります。
大切なのは、“正解を探すこと”ではなく、
本人の想いを理解しようとする姿勢です。
本人の意思を知らないまま決断するリスク
本人が元気なうちに希望を伝えていないと、
家族が突然の場面で決断を迫られます。
その結果、
- 家族間で意見が分かれる
- 医療現場で混乱する
- 後から「本当にこれで良かったのか」と悩み続ける
というケースも少なくありません。
家族で話し合うときのポイント
「どう生きたいか」を中心に話す
「延命治療をするかどうか」だけでなく、
“どんな最期を迎えたいか” を話し合うことが大切です。
たとえば、
- 最後まで自宅で過ごしたい
- 苦しみをできるだけ少なくしたい
- 家族に迷惑をかけたくない
こうした価値観を共有することで、
家族全員が納得できる形を見つけやすくなります。
「医療行為」ではなく「生き方」を共有する
医療の選択は難しいですが、
「生き方」や「願い」を軸に話すと、自然に答えが見えてきます。
「本人がどう過ごしたいと思っているか」
この視点が、医療の判断を支える最も大切な基準になります。
事前指示書(リビングウィル)の活用方法
書き方と伝え方のポイント
事前指示書(リビングウィル)とは、
延命治療や医療方針について本人があらかじめ意思を示す書面のことです。
内容の一例:
- 人工呼吸器・経管栄養を希望するか
- 苦痛緩和を優先するか
- 最期をどこで迎えたいか
書き方に決まりはなく、ノートやメモでも構いません。
家族やかかりつけ医に伝えておくことが大切です。
終活ノートに記録しておくメリット
終活ノートに延命治療の希望を書いておくことで、
家族が判断に迷ったときの大きな助けになります。
また、法的効力はなくても、
本人の想いを尊重する根拠として強い意味を持ちます。
まとめ|延命治療は“命の選択”ではなく“想いの共有”
延命治療は「生かす・やめる」を選ぶ話ではなく、
「どう生きたいか」「どう見送りたいか」を話し合うきっかけです。
元気なうちに家族で話しておくことが、
後悔のない選択と穏やかな時間につながります。
📚 参考・出典
・
厚生労働省「人生会議(ACP)を始めましょう」
・
一般社団法人 日本尊厳死協会「リビングウィルとは」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。