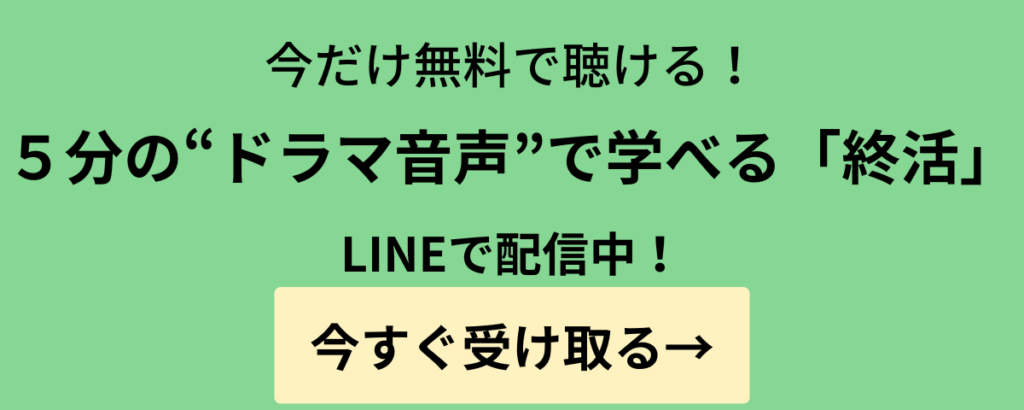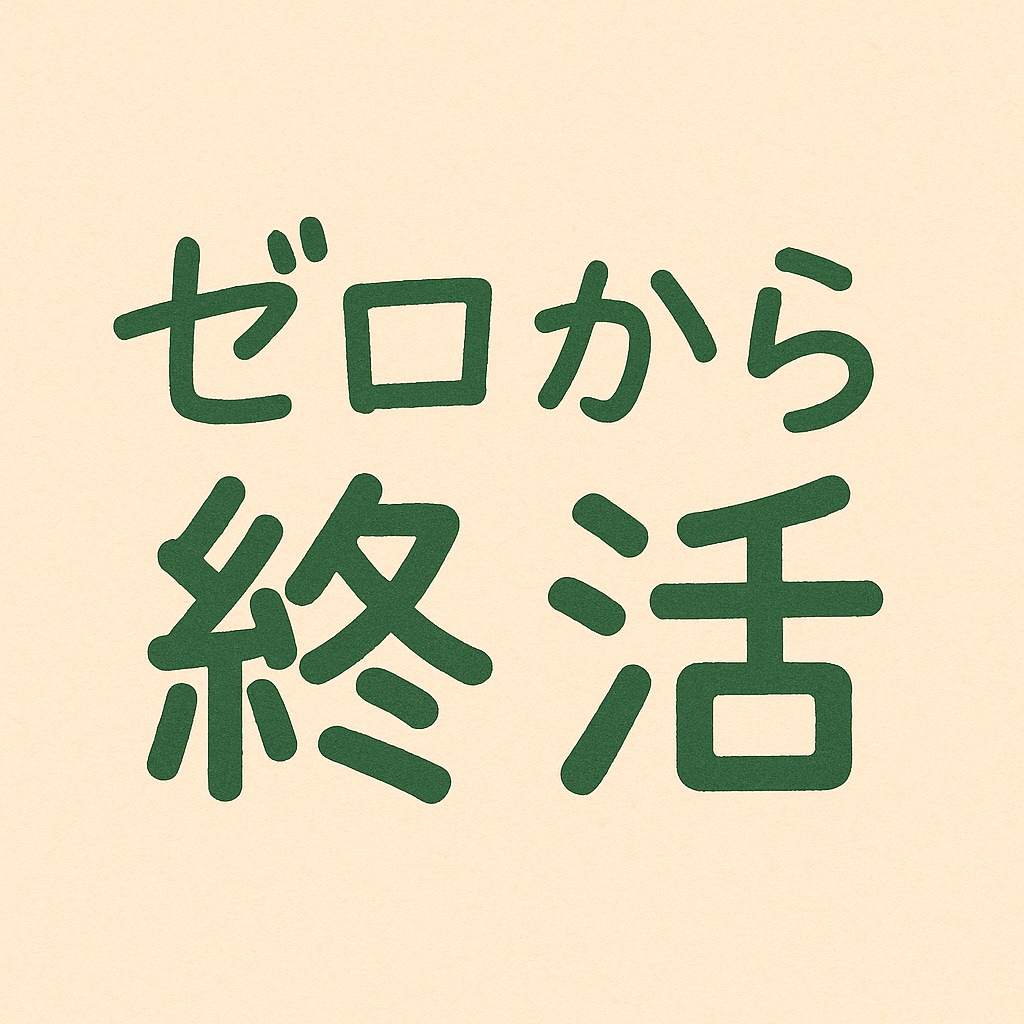介護費用はいくらかかる?在宅と施設の違いを比較
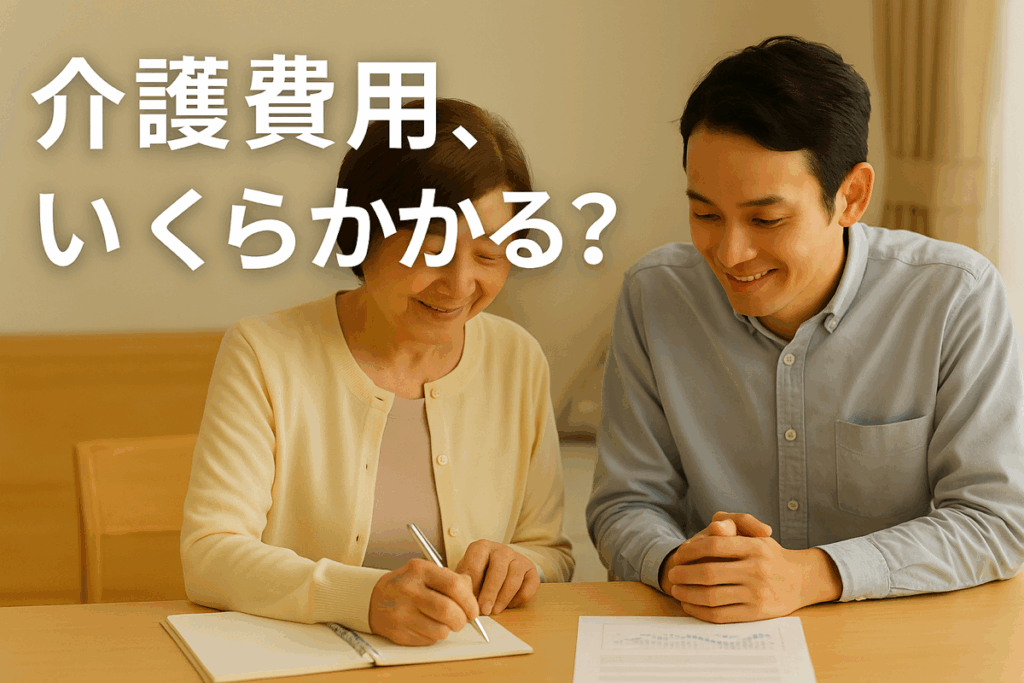
「親の介護、いったいどれくらいお金がかかるの?」
──そう感じたことはありませんか?
介護は、誰にとっても身近で避けられないテーマ。
しかし、「平均費用」や「制度の仕組み」を知らないまま準備を始めると、
家計への負担が大きくなってしまうこともあります。
この記事では、在宅介護と施設介護の費用の違いをわかりやすく比較しながら、
介護保険でカバーされる範囲や、費用を抑えるための制度も解説します。
これから親の介護を考える方に、現実的な目安と安心をお届けします。
介護費用の全国平均はいくら?
在宅介護と施設介護の費用の違い
厚生労働省の調査によると、介護にかかる月額費用の全国平均は約8万〜12万円です。
ただし、「どこで」「どんな介護を受けるか」によって、金額は大きく変わります。
| 介護の形態 | 平均月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 約8〜10万円 | デイサービス・訪問介護・福祉用具など |
| 介護付き有料老人ホーム | 約20〜25万円 | 介護サービス+居住費・食費を含む |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 約10〜15万円 | 公的施設で比較的安価だが入所待ち多い |
介護サービス別の費用目安(デイサービス・訪問介護など)
| サービス名 | 自己負担額(月額目安) | 利用例 |
|---|---|---|
| デイサービス | 約1〜3万円 | 週2〜3回の通所介護 |
| 訪問介護(ヘルパー) | 約1〜2万円 | 家事・入浴介助など |
| ショートステイ | 約1〜3万円/回 | 数日の宿泊介護 |
| 福祉用具レンタル | 約1,000〜2,000円/月 | ベッド・車椅子など |
※自己負担1割(介護保険適用)で計算した場合
介護費用がかかる理由と内訳
介護保険でカバーされる部分
介護保険では、要介護認定を受けることで
介護サービス費用の原則1〜3割負担で利用できます。
つまり、残りの7〜9割は国や自治体が負担しています。
対象となるのは以下のような「在宅・施設サービス」です:
- 訪問介護・看護・入浴
- デイサービス(通所介護)
- ショートステイ(短期入所)
- 福祉用具レンタル・住宅改修 など
自己負担が増えるケース(介護度・所得・加算など)
次のような場合には、想定より費用が増えることがあります。
- 要介護度が高く、利用回数が増える
- 所得が一定以上あり、自己負担割合が2〜3割に引き上げ
- 夜間・休日などの加算料金
- 居住費・食費・医療費など、介護保険外の支出
このため、「介護費用=介護サービス費」だけでなく、
トータル支出を把握することが大切です。
在宅介護と施設介護を比較
メリット・デメリットを表で解説
| 項目 | 在宅介護 | 施設介護 |
|---|---|---|
| 費用 | 安い(平均8〜10万円) | 高い(平均20万円以上) |
| 介護者の負担 | 家族の負担が大きい | スタッフが中心で軽減される |
| 安心感 | 家で過ごせる安心 | 専門スタッフが常駐 |
| 柔軟性 | 家族の希望に合わせやすい | 施設のルールに従う必要あり |
家族の負担・費用バランスを考えるポイント
「親が家で過ごしたい」と思っても、
家族の仕事・生活・距離によっては在宅介護が難しいこともあります。
その場合は、“できる部分だけ家族が関わる”折衷型を検討するのも一つの方法。
(例:平日はデイサービス、週末は家族がケア)
介護費用を抑えるための制度・助成金
高額介護サービス費制度
介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合、
超過分が払い戻される制度です。
上限は所得によって異なりますが、
多くの世帯では月額4〜5万円程度が上限となります。
介護保険外で使える補助・税控除
介護関連で利用できる主な補助・控除には、次のようなものがあります。
- 医療費控除(オムツ代や通院交通費も対象になる場合あり)
- 住宅改修の補助金(段差解消・手すり設置など)
- 自治体独自の介護補助制度(地域によって異なる)
申請窓口は市区町村の介護保険課。
知らずに損している人も多いため、一度確認しておく価値があります。
まとめ|費用を知ることが“安心の第一歩”
介護費用は、「知ること」から始まります。
平均額を把握しておけば、いざというとき焦らずに行動できます。
家族で介護の方針を話し合うときは、
「どこで」「誰が」「どんなサポートを受けるか」を
具体的に決めておくのがおすすめです。
📚 参考・出典
・
厚生労働省「介護サービス利用者負担」
・
厚生労働省「介護保険制度の概要」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。