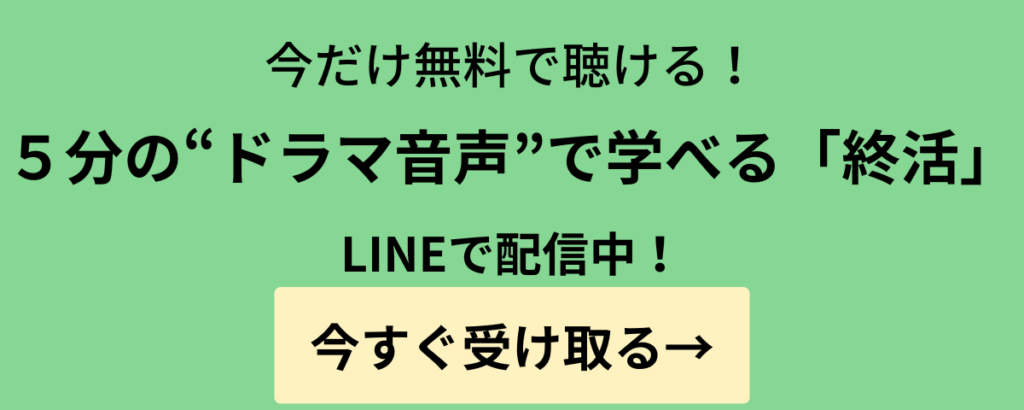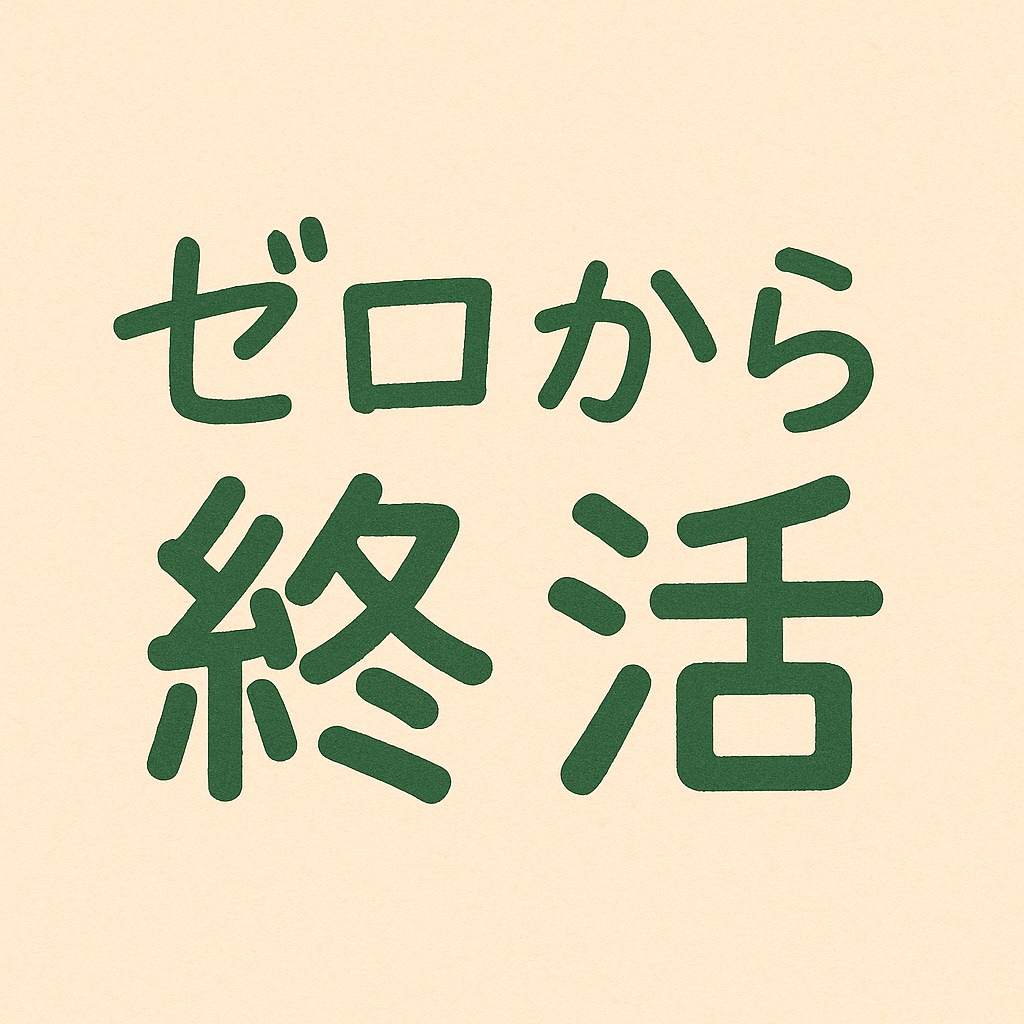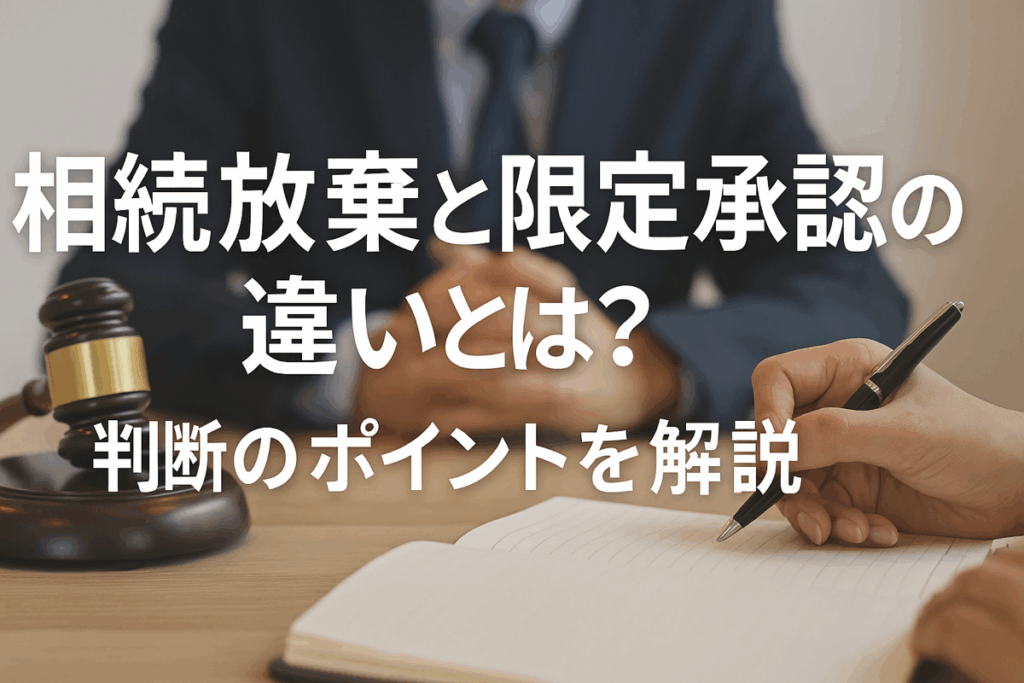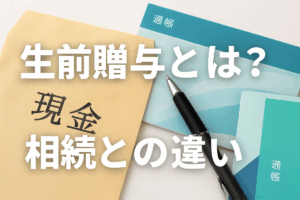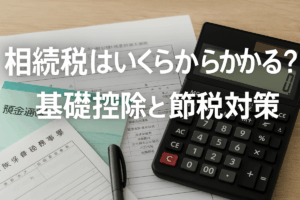家族信託とは?認知症対策になる新しい財産管理の仕組み
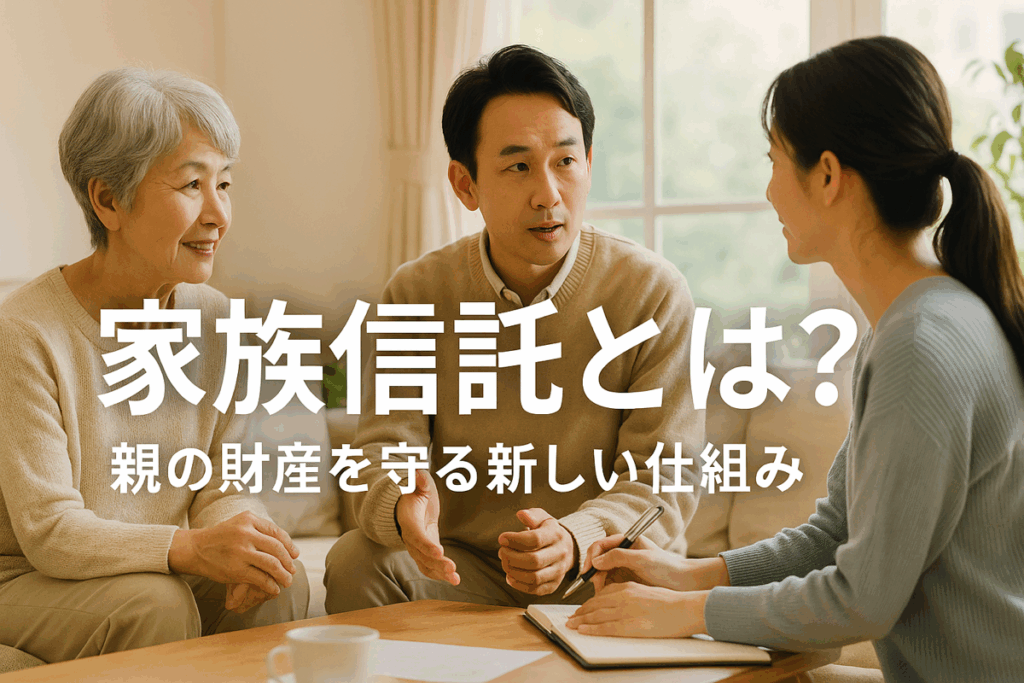
「もし親が認知症になったら、預金が使えなくなるって本当?」
──そう聞いて、驚かれる方も多いのではないでしょうか。
実は、本人の判断能力が低下すると、
銀行口座の凍結や不動産の売却ができなくなるケースがあります。
そんな“万が一”に備える方法のひとつが、
今注目されている 「家族信託(かぞくしんたく)」 です。
この記事では、家族信託の基本構造から
成年後見制度との違い、メリット・注意点までをわかりやすく解説します。
家族信託とは?仕組みを簡単に
信託の基本構造(委託者・受託者・受益者)
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう制度です。
登場人物は3つ。
- 委託者:財産を預ける人(親など)
- 受託者:財産を預かり、管理・運用する人(子など)
- 受益者:利益を受ける人(通常は親本人)
たとえば、親が子に財産を託し、子が代わりに不動産を管理・処分できる仕組みです。
財産を“預けて管理する”仕組み
家族信託では、財産の名義を一時的に受託者(子など)に移します。
ただし、所有権は形式的に移っても、実質的な利益は委託者本人(親)に残るため、安心です。
このしくみにより、親が認知症になったあとでも、
家族が代わりに資産を管理・売却できるようになります。
成年後見制度との違い
手続き・柔軟性の違い
成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理します。
一方、家族信託は自分で“誰に託すか”を決めておける点が大きな違い。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 管理者 | 家族(信頼できる人) | 裁判所が選任 |
| 管理内容 | 契約で柔軟に設定できる | 法で厳格に制限 |
| 費用 | 契約書・登記など初期費用あり | 維持費(報酬)あり |
| 柔軟性 | ◎ 高い | △ 制限が多い |
併用できるケースも
家族信託と成年後見制度は併用も可能です。
たとえば、財産管理は家族信託、身の回りの法律行為は成年後見人、という分担もあります。
どちらか一方で完璧に対応できるわけではないため、目的に応じた選択が重要です。
家族信託のメリット・デメリット
自由度の高さと費用負担
【メリット】
- 認知症になっても財産の凍結を防げる
- 家族間で柔軟な管理ができる
- 相続対策・二次相続にも活用可能
【デメリット】
- 契約書作成や登記に専門的な知識が必要
- 税金・手数料など初期費用がかかる(約20〜50万円が目安)
トラブル回避のための注意点
家族信託は「信頼関係」が前提。
受託者が勝手に財産を動かすリスクを防ぐために、
契約書に詳細な管理ルールを明記し、公正証書化することが推奨されます。
信託契約の作り方と流れ
契約書作成から登記まで
家族信託は、基本的に以下の流れで行います:
1️⃣ 家族間で目的・内容を話し合う
2️⃣ 専門家(司法書士・弁護士)に相談
3️⃣ 契約書を作成(必要に応じて公正証書)
4️⃣ 不動産がある場合は登記手続き
専門家の関与が必要な場合
信託財産に不動産・株式・賃貸物件が含まれる場合、
登記や税務が関係するため、司法書士・税理士のサポートが必要になります。
複雑な契約内容にしないこともトラブル防止のコツです。
まとめ|“もしもの前に”できる安心対策
家族信託は、「認知症になる前」にしか始められません。
判断能力があるうちに話し合い、契約を結ぶことが大切です。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、
「元気な今だからできる」——それが家族信託の本質です。
親の安心と家族の負担軽減、
その両方を守るために、早めの準備を始めましょう。
📚 参考・出典
・
法務省「家族信託とは?」
・
一般社団法人相続手続支援センター「家族信託」
・
厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
・
日本弁護士連合会「民事信託と後見制度」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。