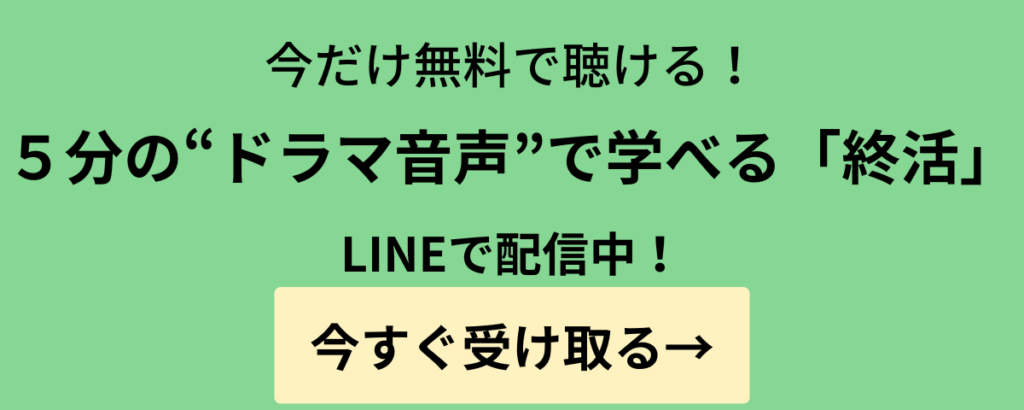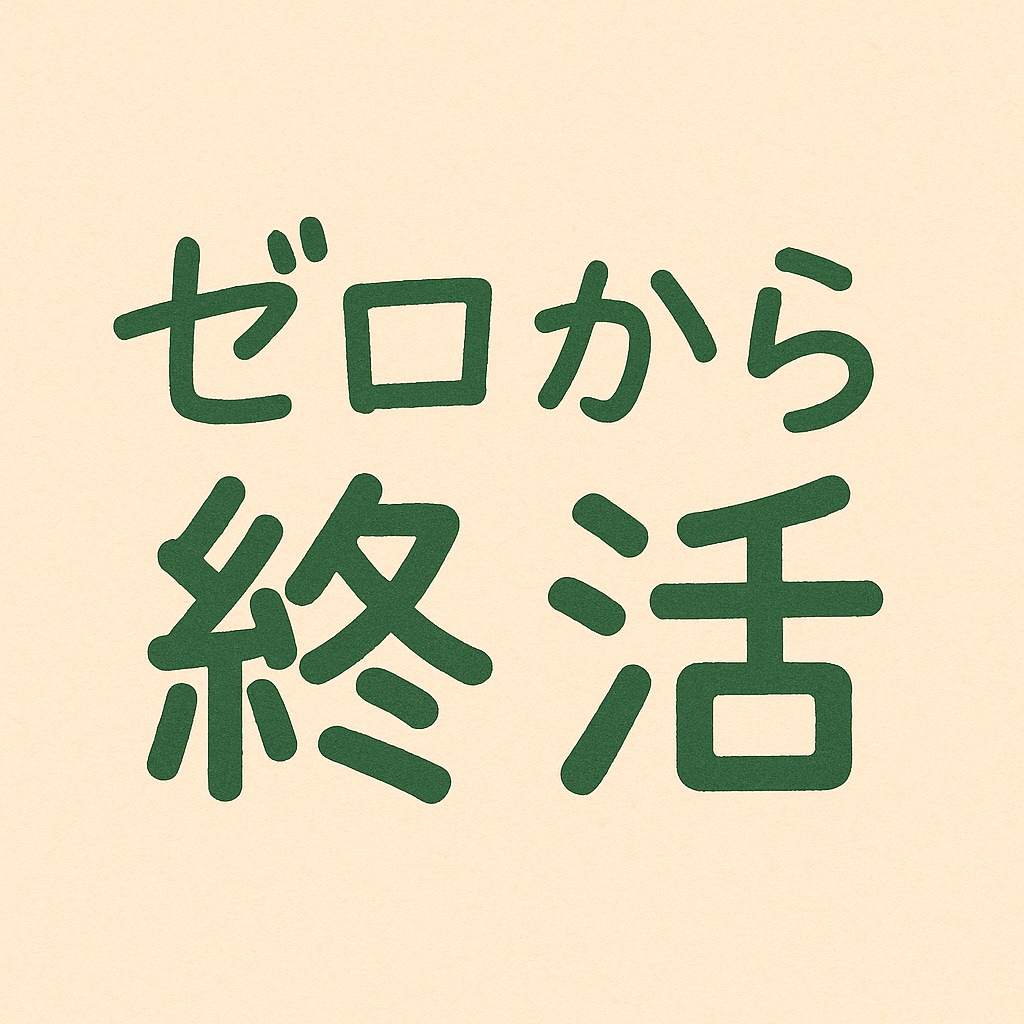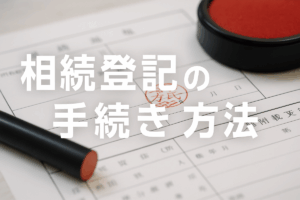生前贈与とは?相続との違いと節税のポイントを解説
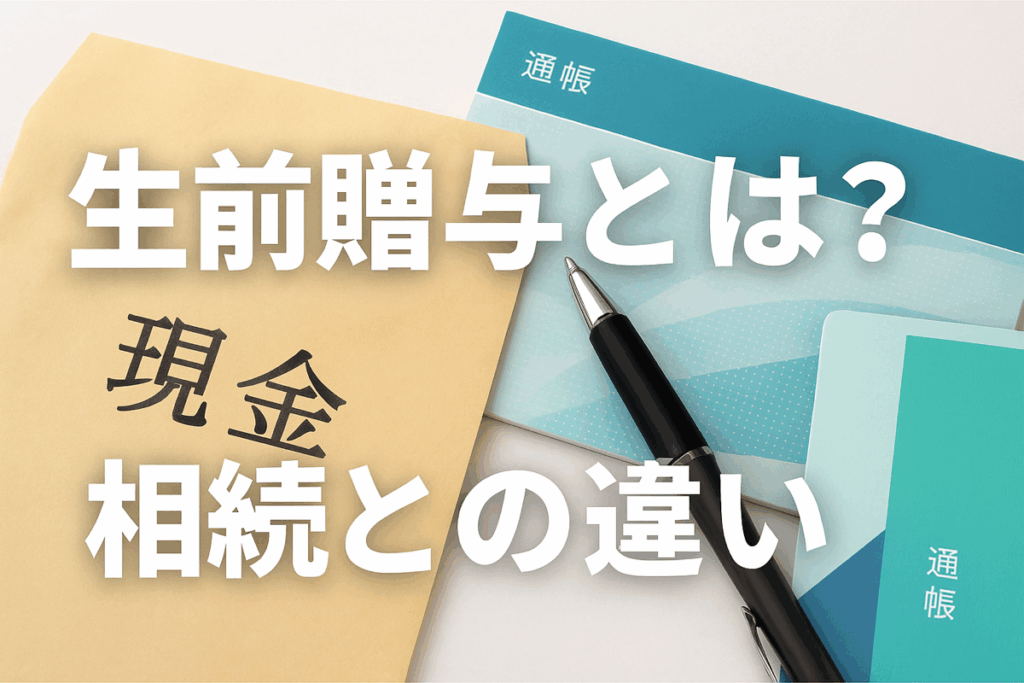
「相続税がかかる前に、少しずつ子どもへ財産を渡したい」
そんなときに検討されるのが “生前贈与” です。
生前贈与は、亡くなる前に財産を贈ることで、
相続税の節税や円滑な財産承継に役立つ方法です。
ただし、手続きや税金の仕組みを理解していないと、
「贈与したつもりが課税対象になる」ことも。
この記事では、相続との違い・メリット・注意点をわかりやすく解説します。
生前贈与とは?相続との違い
生前贈与の定義
生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で他人に渡すことです。
たとえば、親が子どもにお金や不動産を贈る場合などが該当します。
一方の「相続」は、亡くなった後に財産を承継する仕組み。
どちらも“財産の移転”という点では同じですが、時期と税金の扱いが大きく違います。
相続との大きな違い
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 財産を渡す時期 | 生前 | 死後 |
| 税金の種類 | 贈与税 | 相続税 |
| 主なメリット | 節税・トラブル回避 | 財産を一括承継できる |
| 手続き | 契約書など個人で可 | 法定相続人による手続き |
特に贈与税は、「相続税よりも高い」と誤解されがちですが、
正しく計画的に行えば、節税効果が得られます。
生前贈与のメリット・デメリット
節税効果が期待できる
生前贈与の最大のメリットは、相続税の対象となる財産を減らせること。
年間110万円までなら「贈与税がかからない」ため、
数年かけて計画的に財産を分けておけば、相続時の負担を大きく減らせます。
また、教育資金や住宅取得資金の特例を活用すれば、
さらに非課税枠を拡大することも可能です。
贈与後のトラブルリスク
注意したいのは、「贈与の意思表示が曖昧」なまま渡すケース。
口頭だけで渡すと「贈与されたものではない」と主張され、
兄弟間のトラブルに発展することもあります。
また、贈与後3年以内に亡くなった場合、相続財産に含まれるケースもあるため注意が必要です。
贈与税の仕組みと控除額
年間110万円まで非課税
贈与税は、もらう側に課税されます。
ただし、1人あたり年間110万円までは非課税です。
たとえば、毎年100万円を10年間贈与すれば、合計1,000万円を非課税で渡せます。
複数の子ども・孫に分けて贈与すれば、より効果的な資産移転が可能です。
教育・住宅資金の特例
特例を利用すれば、さらに大きな金額を非課税で贈与できます。
- 教育資金:最大1,500万円まで非課税(一定条件あり)
- 住宅取得資金:最大1,000万円まで非課税(2025年12月末まで延長)
これらは贈与契約書と領収証の保存が条件です。
「口座からの振込」「使途の明確化」を忘れずに。
失敗しないための注意点
名義預金扱いにならないように
親が子の名義で口座を作り、勝手に貯金している場合、
それは名義預金(贈与ではない)と判断されることがあります。
重要なのは「子が自由に使える状態であること」。
振込記録を残して、贈与の意思を明確にしましょう。
証拠(贈与契約書)を残す
贈与契約書を作ることで、後のトラブル防止になります。
簡単なもので構いませんが、
- 贈与する日付
- 金額
- 贈与する側・受け取る側の署名押印
を明記しておくと安心です。
まとめ|計画的な贈与が“家族の安心”に
生前贈与は、節税だけでなく、家族の気持ちを整理する手段でもあります。
相続のトラブルを防ぎたい、子どもに早く財産を託したい——
そう感じたときが、最初の一歩です。
大切なのは、ルールを理解し、無理のない範囲で計画的に行うこと。
「生きているうちに想いを伝える贈与」が、
後悔のない相続準備につながります。
📚 参考・出典
・
国税庁「贈与税のしくみ」
・
国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
・
国税庁「相続税・贈与税」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。