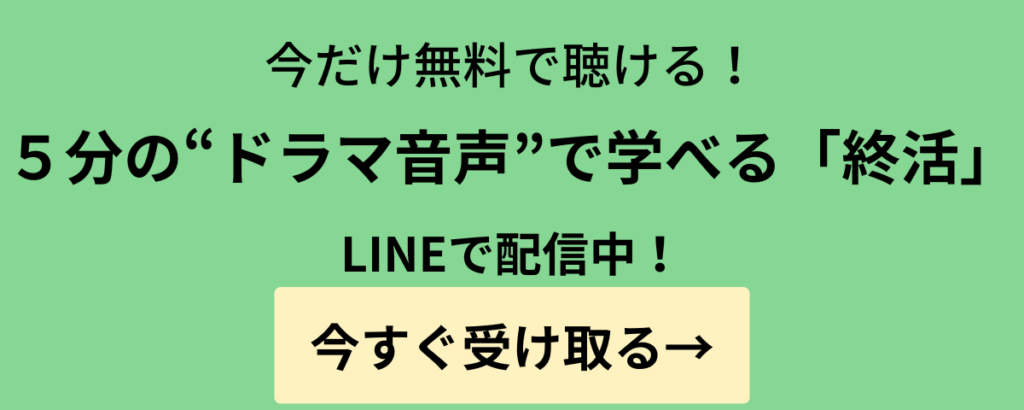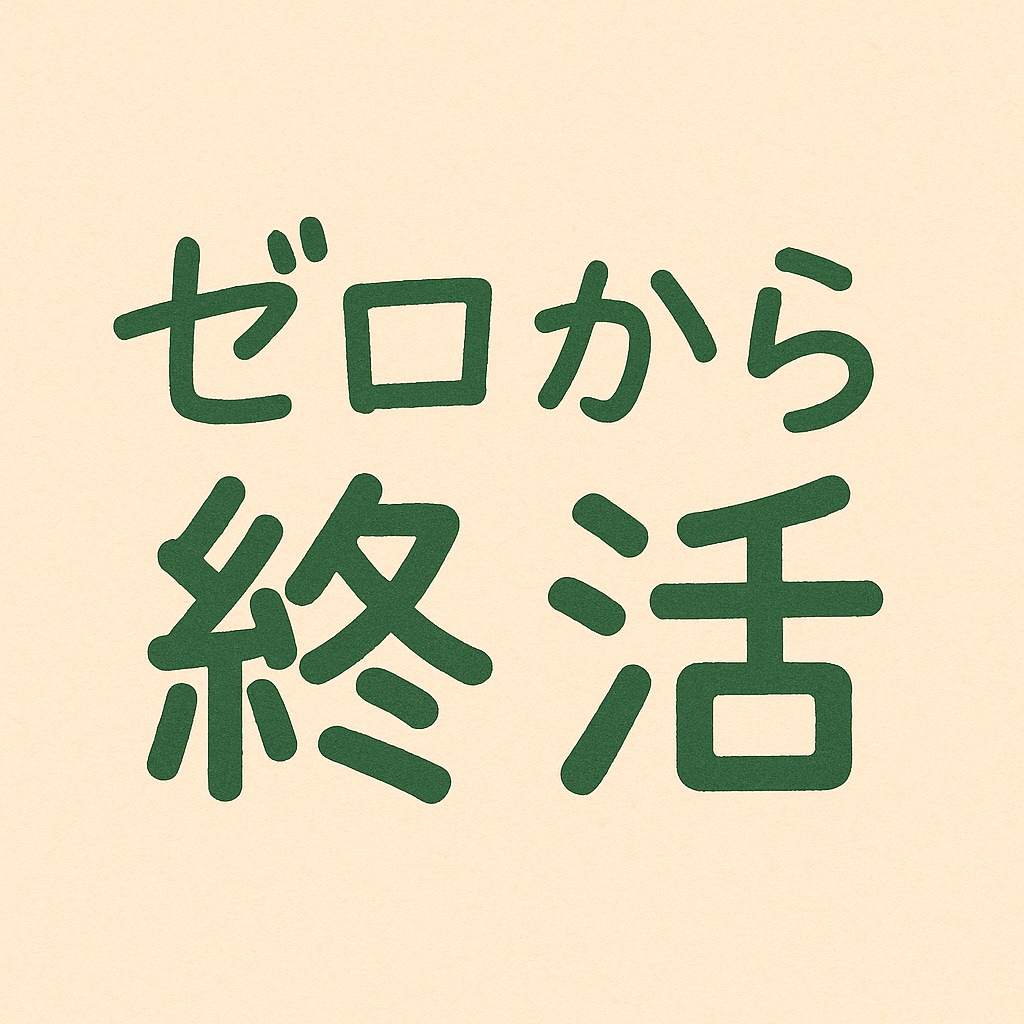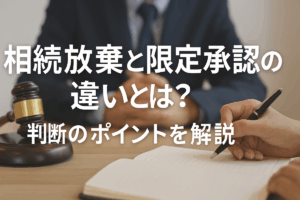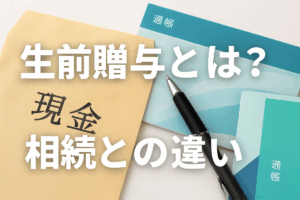相続登記の手続き方法|初心者でもわかる必要書類と流れ

「不動産の名義、まだ親のままになっているけど大丈夫?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
登記を放置すると、罰金(過料)が発生する可能性もあります。
この記事では、相続登記の基本の流れや必要書類、
そして司法書士に依頼する場合の費用や注意点を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
相続登記とは?義務化の背景
なぜ義務化されたのか
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった人から相続人へ移す手続きです。
これまで義務ではありませんでしたが、
名義放置によって「所有者不明土地」が全国的に増加したため、
2024年4月から法改正により義務化されました。
登記を怠ると土地の活用ができず、公共事業や売却の妨げになるケースも多発しています。
名義の放置が招くリスク
名義をそのままにしておくと、
- 売却・賃貸ができない
- 固定資産税の納付者が不明
- 相続人が増え、話がまとまらなくなる
といったリスクがあります。
特に、相続人が複数に増えると、1件の登記に数年かかることも。
「登記はあとで」と後回しにせず、早めの対応が大切です。
相続登記の基本の流れ
① 相続人の調査
まず、誰が相続人になるのかを確定させます。
戸籍謄本をたどって、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までを確認し、
全ての相続人を特定します。
司法書士に依頼する場合、この調査を代行してもらうことも可能です。
② 遺産分割協議書の作成
次に、不動産を誰が相続するかを話し合い、全員の合意をもとに協議書を作成します。
協議書には、相続人全員の署名・実印が必要です。
1人でも署名が欠けると無効になるため、慎重に確認しましょう。
③ 登記申請書の提出
遺産分割協議書と必要書類をそろえたら、
不動産所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
申請は窓口だけでなく、郵送・オンラインでも可能です。
必要書類一覧と注意点
戸籍・印鑑証明などの準備
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 登記申請書
- 固定資産評価証明書
これらは市区町村役場や法務局で取得できます。
不備が起きやすい箇所
特に注意したいのが、戸籍の抜け漏れと住所の相違です。
登記簿上の住所と住民票の住所が異なる場合、補足書類が必要になります。
書類は一つでも不足すると受理されないため、提出前に再チェックを。
司法書士に依頼するメリット
費用と依頼の流れ
司法書士に依頼する場合、費用の目安は5〜10万円前後。
内容や地域によって異なりますが、
「書類の不備で差し戻しになるリスクを避けたい」という方にとっては有効です。
依頼から完了までの流れは以下の通りです。
1️⃣ 書類の確認・見積もり
2️⃣ 必要書類の取得代行
3️⃣ 登記申請・完了報告
トラブル防止のための専門知識
司法書士は、登記申請に関する法的判断のプロ。
名義が複雑な場合や相続人が多い場合、
スムーズな登記を進めるために専門家のサポートが役立ちます。
「どの書類をいつ出すか」を任せられる安心感も大きなメリットです。
まとめ|“早めの登記”が家族を守る
相続登記の放置は、将来の家族に思わぬ負担を残します。
2024年からの義務化により、
「名義変更は後でいい」が通用しなくなりました。
迷ったらまず、法務局や司法書士に相談してみましょう。
早めに動くことで、“家族の財産”を確実に守ることができます。
📚 参考・出典
・
法務省「相続登記の義務化について(令和5年版)」
・
法務省「相続登記の手続き・申請書の書き方」
・
法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
・
日本司法書士会連合会「相続登記サポートと相談窓口」
※本記事は上記公的機関・団体の一次情報をもとに執筆しています。
最新の法令・制度改正等については各公式サイトをご確認ください。